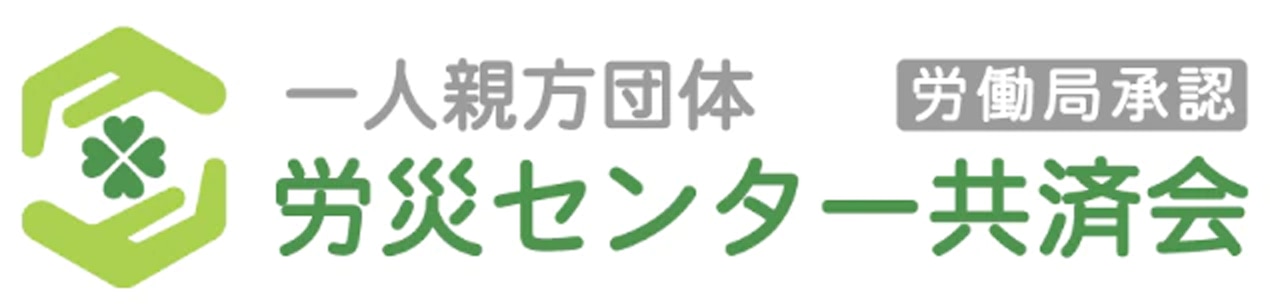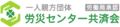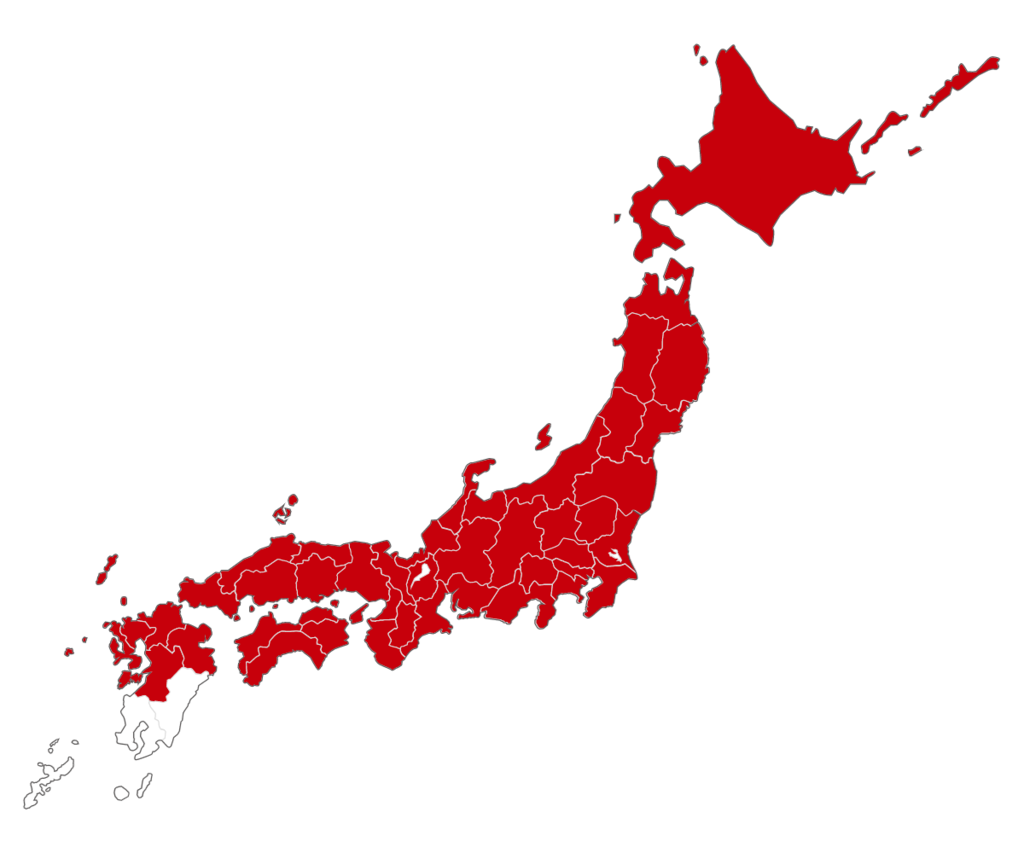労働者供給事業と労働者派遣業の違いとは?一人親方の偽装派遣についても解説

一人親方を派遣すると聞いて、労働者供給事業と労働者派遣業を思い浮かべる方も多いのではないのでしょうか。労働者供給事業と労働者派遣業はどちらも労働者が派遣されて仕事を行う方法です。
しかし、労働者供給事業と労働者派遣業には、雇用関係や支配関係、誰が派遣元になれるのかといった違いがあります。また、建設業の一人親方のように請負契約において建設業に従事する方もいます。
請負業の場合、労働者供給事業や労働者派遣業は関係のないことのように思えますが、実は知っておかないと法律に関わることもあります。
この記事では労働者供給事業と労働者派遣業の違い、一人親方のような業務の依頼や派遣などの請負業について解説致します。人材派遣事業の基盤となる職業安定法にある禁止事項などについてよく知っておき、違法な環境で仕事をしたり、させたりしないようにしましょう。
目次[非表示]
- 1.労働者供給事業、労働者派遣業及び請負業とは?
- 2.労働者供給事業と労働者派遣業の違いとは?
- 2.1.雇用関係と支配関係
- 2.2.営利目的での営業の許可
- 2.3.在籍出向とは?
- 2.4.労働者派遣業が可能な業種
- 3.人材紹介業に関わる職業安定法とは
- 4.職業安定法の基本事項
- 5.職業安定法での禁止事項
- 5.1.手数料に関する禁止事項
- 5.2.紹介が禁止されている職業
- 5.3.労働者に明示すべき事項
- 6.偽装一人親方の問題
- 7.まとめ
労働者供給事業、労働者派遣業及び請負業とは?
労働者供給事業はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、労働者派遣事業や請負業を理解する上で欠かせない言葉です。
- 労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものを含まないとされています。
- 労働者派遣事業とは、自己の雇用する労働者を、雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、他人のために労働に従事させることをいい、他人に対し労働者を他人に雇用させるこ とを約してするものを含まないものとする。
- 請負とは当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
このうち1の労働者供給事業については、労働組合が認可を受けた場合を除き全面的に禁止されています。また、労働者派遣法の第4条において「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」については労働者派遣事業を行ってはならないとあります。したがって、建設業においては3の請負業のみ合法となります。
労働者供給事業と労働者派遣業の違いとは?
労働者供給事業と労働者派遣業は一見すると似たような形態に思えますが、実は大きな違いがあります。この違いを理解しておかないと、思わぬトラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。
では、労働者供給事業と派遣の違いを2つ見ていきましょう。
雇用関係と支配関係
労働者供給事業と派遣の大きな違いとなるのが、雇用関係と支配関係です。労働者派遣業の場合、労働者と派遣元の会社が雇用関係を結び、労働者は他の企業に働きに行きます。
指揮命令は派遣先の企業が行い、賃金は派遣元が労働者に支払う形になります。派遣社員として働いている方も多いので、派遣の構造を理解するのはそれほど難しくないでしょう。
一方で、労働者供給事業では、供給元と労働者との間に支配関係があったり、供給先と労働者間に雇用契約があったりします。労働者供給事業は、供給元が支配関係を利用して労働者の賃金を着服するといったリスクが排除できないため、労働者派遣業を除いて全面的に禁止されています。
営利目的での営業の許可
雇用関係と支配関係からわかるように、労働者供給事業は労働者にとって大きなリスクがあります。したがって、労働者の利益が保護されないという観点から、基本的には禁止されています。
ただし、派遣に関しては厚生労働省の許可を得た場合に限って営利目的で事業を営むことが可能です。一方で、労働者供給事業は営利目的での事業は許可されません。
労働者供給事業で唯一許可されるのは、必ず労働者の利益を優先できる労働組合が無料で行う場合に限られます。
つまり、労働者供給事業の中で特例として認められているのが、労働者派遣業であるという構造になっているのです。そのため許可という形式で、労働者派遣業を営む事業者には大きな制約を課しています。
在籍出向とは?
労働者供給事業に類似したものとして、在籍出向という制度があります。在籍出向とは、出向元と雇用契約を維持しながら出向先との間においても雇用関係が発生させ、それに基づき労務提供を行うというものです。この在籍出向は、次のような要件を満たす場合に限り違法とはされておりません
在籍型出向のうち、次のような目的を有しているものについては、出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと解釈されています。
- 労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する
- 経営指導、技術指導の実施
- 職業能力開発の一環として行う
- 企業グループ内の人事交流の一環として行う
労働者派遣業が可能な業種
特別に許可を受けた労働者派遣業においても、なお禁止されている業種というものが存在します。労働者派遣法では、労働者派遣事業を行うことができない業務を次のように定めています。
- 港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)
- 建設業務(建設の現場作業に係るもの)
- 警備業務(警備業法上の警備業務)
- 紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務)
この中でも注目すべきは、やはり建設業務でしょう。なぜ建設業務において派遣が禁止されているかというと、建設業は下請重層構造が常態化しており指揮命令関係が分かりづらため、雇用契約及び指揮命令関係を明確化して労働者を保護するためと言われいます。
人材紹介業に関わる職業安定法とは

人材紹介業や派遣業務に関する重要な法律の一つが「職業安定法」です。職業安定法とは、労働者が就職する機会を与え、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的とした法律です。
職業安定法は、とくに人材紹介業にかかわる法律であり、人材派遣会社やそこで働く労働者が知っておくべきものといえます。
職業安定法の基本事項
職業安定法にはさまざまな条項がありますが、人材派遣において重要なポイントは覚えておく必要があります。たとえば、第2条では基本的に誰でも自分の職業を自由に選択することができると保証されています。
さらに第3条によれば、職業紹介などの事業において、人種や国籍、性別、宗教的・政治的信条、身分などによって差別を受けることはありません。
加えて、第44によって、労働組合が厚生労働省の許可を得て無料で行う場合を除いて、労働者供給事業は禁止されているのです。派遣については、第4条で労働者供給事業に含まれないと規定されています。
職業安定法での禁止事項
職業安定法は、人材派遣にかかわる重要な法律で、禁止事項も多く規定されています。派遣は労働者供給事業の中で許可されている事業であり、基本的に労働者の立場が弱いからです。
職業安定法における禁止事項を知っておかないと、トラブルが起きた際、知らないうちに不利益を被ったりしてしまうかもしれません。
では、職業安定法での禁止事項を3つ見ていきましょう。
手数料に関する禁止事項
人材派遣の手数料については、職業安定法によって非常に厳しくルールが設けられています。派遣元の企業としては、少しでも多くの手数料を取った方が多くの利益を得られるはずです。
しかし手数料に関しては、人材派遣業者が絶対に守らなければならない禁止事項があります。まず、労働者から手数料を徴収することは原則禁じられています。
モデルや経営管理者、熟練技能者などわずかな例外を除いて、労働者から手数料を徴収することはできません。
そもそも人材派遣事業に登録している労働者は経済的に余裕があることが少ないので、手数料によってさらなる負担をかけないようにするためです。さらに、人材派遣によって得られる手数料の上限が決められています。
手数料の上限は、税込みで6ヶ月間の賃金総額の11%です。さらに受付手数料として1件あたり710円を受け取ることもできます。これ以上の手数料を受け取りたい場合には、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
紹介が禁止されている職業
人材派遣事業でも、労働者に紹介してはいけない職業があり、港湾運送業務、建設業務は、全面的に紹介が禁止されています。
さらに、人材派遣会社が事前に厚生労働大臣に届け出た範囲で、人材派遣を行わなければならないことも定められています。
労働者に明示すべき事項
職業安定法では、人材派遣会社が労働者に明示すべき事項が決められています。この事項を示さずに労働者を派遣することは禁止されているのです。
たとえば、取扱い職種、手数料、苦情の処理方法、個人情報の取り扱い、払戻金の制度については、書面で明示することが求められています。
こうした禁止事項に抵触してしまうと、業務停止命令や人材派遣事業の許可の取り消し、懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科せられる恐れがあります。
偽装一人親方の問題
以前、偽装一人親方とは。現場の実態や対策について解説において、偽装一人親方の問題を解説いたしました。実態として、元請け等の指揮命令等を受けて仕事をしておきながら契約上は、請負契約を締結して社会保険料の節約や労働関係法令の適用を逃れるというものでした。
この問題は、労働者供給事業や労働者派遣業の問題であるともいえます。繰り返しになりますが、労働者供給事業は全面的に禁止です。許可を受けて事業を営む労働者派遣業においても、建設業務は禁止されております。
請負契約と言いつつ、実態は建設業従事者を派遣し現地で元請け等の指揮命令を受けて業務に従事させることは、明確に法律に違反していると言えます。
建設業における労働者派遣、なぜ禁止?
労働者派遣事業において、建設業の派遣が禁止されている理由はなぜでしょうか?
一般的に建設業は重層的な下請関係で業務の処理が行われていますが、そこで働く労働者と指揮命令する者とが一致する、つまり直接雇用の形態となるように契約関係の明確化が図られております。建設業務に労働者派遣を導入した場合、契約関係が複雑になり指揮命令関係や責任の所在が曖昧になりかねない、という理由から建設業の労働者派遣は禁止されております。
まとめ
労働者供給事業は労働者の利益を守るため、基本的に全面的に禁止されており、厚生労働大臣の許可を得た場合にのみ行うことができます。人材派遣会社に求められる条件も高く、労働者が不利益を被らないような工夫がなされているのです。
ただし、実際に人材派遣会社が法律を順守している保証はないので、労働者の側も職業安定法や禁止事項についてよく知り、よい環境で働けるようにしましょう。
また、一人親方はいろいろな方から依頼されて仕事をすることがおおいでしょう。その時々でどのような契約で仕事をしているのか、日雇い派遣のような仕事をしても、それは厳密な意味での一人親方としての仕事とはなりません。充分に注意してください。