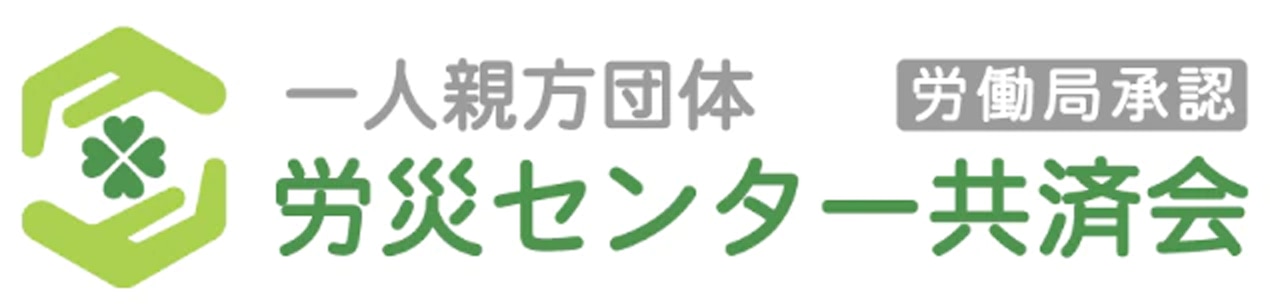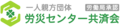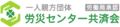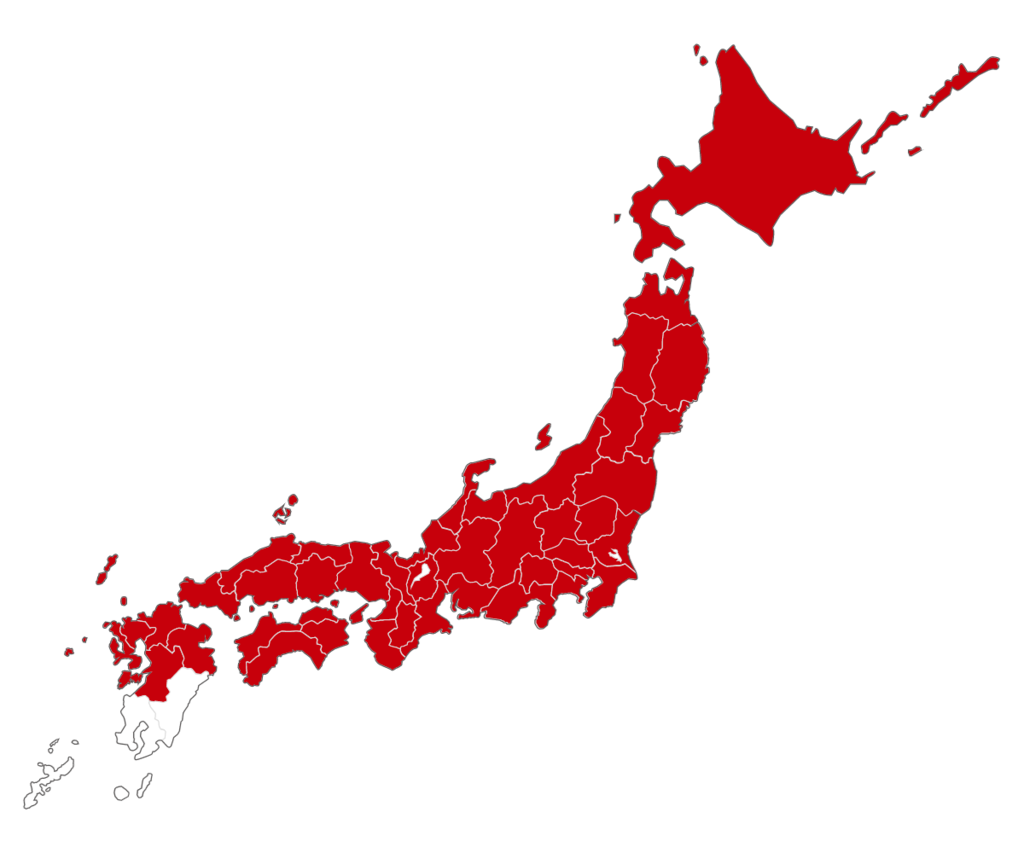労災保険で請求できる移送費や治療用装具費に関する基礎知識

仕事が原因のケガや疾病、又は通勤途上でのケガに対して労災保険は療養(補償)給付として治療に関する様々な給付があります。労働災害のおける労災保険の治療費等の請求を解説します!では療養(補償)給付について解説いたしました。
労災保険には医療機関での治療や薬局での薬の処方以外にも医療機関に行くためにかかった通院費やギプス代などの治療装具費を給付する仕組みがあります。本記事では治療のためにかかった通院費(移送費)や治療装具費が支給される条件と申請方法をご紹介します。
目次[非表示]
労働中に起きた怪我は「労働災害」として認められ、治療費や怪我による休業分の給料(一部)、障害が残ってしまった場合には介護費用や障害給付が補償される仕組みがあります。
ここで忘れてはいけないのが、遠方から病院に通う際に発生する「通院費」です。労災保険には条件を満たした場合に通院費を請求できます。
また怪我によって身体の動きを支える「治療用装具」を着用した場合、治療用装具にかかった費用も労災保険の支給対象です。
今回は労災保険で支給される移送費と治療用装具費に関して、制度の仕組みや条件などを詳しくご紹介します。
なお、移送費も治療用装具も一旦全額を負担した上で、代金の払い戻し手続きの申請を労働基準監督署に行います。この点注意が必要です。
労災保険で支給される移送費や治療用装具費について解説します。
労災保険で移送費や治療用装具費は請求できる?
労災保険では怪我の治療にかかった医療費だけでなく、怪我で仕事を休んだ分の給料(約8割)が給付されるほか、通院にかかった通院費とギプスやハーネスなどの治療用装具費も給付される決まりがあります。
また、労働中の怪我が原因で障害が残ってしまった場合は、年金または一時金と介護費用が給付されます。さらに、万が一労働者が亡くなってしまった場合には遺族年金または一時金が給付されます。
このように労働中に負った怪我や病気に関しては、幅広い援助が受けられるのが特徴です。
労災保険で通院費(移送費)が給付されるための条件
労働中の怪我や病気を治療するために病院に通っており、その通院費の給付を得るためには一定の条件があります。また法律上では、この通院費を「移送費」と呼んでいます。
まず、前提条件として「病院と家または勤務地が片道2㎞以上離れていること」が条件に挙げられます。
そのほかの条件に関しては、次の通りです。
- 同一市町村内にある「労災指定医療機関を」受診した場合
- 同一市町村内に労災指定医療機関がないため、隣接の市町村内にある「労災指定医療機関」を受診した場合
- 同一市町村内および隣接する市町村内に労災指定医療機関がないため、それ以外の最寄りの「労災指定医療機関」を受診した場合
つまり、労災指定医療機関に認定されており、怪我や病気の治療に適した病院で、なおかつ自宅や職場から最寄りのを受診した場合に移送費としての給付が認められます。
給付額は実費に相当する額です。
条件のうち「労災指定医療機関」という点が重要で、労災指定医療機関以外の病院に通った場合は移送費が支給されません。労災指定医療機関は労働中の怪我や病気を無償で治療できる病院で、厚生労働省が運営する「労災保険指定医療機関検索」のサイトから検索できます。
労災保険で治療用装具にかかる費用が給付されるための条件
怪我の治療に治療用装具が必要になった場合は、使用した治療用装具も払い戻しとして費用が給付されます。
ただし自己判断で購入した治療用装具は給付の対象ではありません。条件は次の通りです。
- 病院で診察を受け、医師による処方がある
また労災保険が支給される治療用器具の例は以下の通りです。
- 人工膀胱
- 人工肛門受便器
- 浣腸材
- ソフトコンタクトレンズ
- 義眼
- 義歯
- コルセット
- 歩行補助器
- 松葉づえ
- 義歯装着前の訓練用装具
- 固定用伸縮性包帯
- 保護防止
- ポリネック
- フローテーションパッド
- 減菌ガーゼ
ただし各器具には条件があるので、事前にしっかり確認する必要があります。
労災保険で請求できる移送費の種類や申請方法

続いて、労災保険で請求できる移送費の種類と、それぞれの申請方法を解説していきます。
労災保険で請求できる移送費の種類
労働中の怪我や病気を治癒する際に通院にかかる費用を支給するためのものですが、本人の通院費以外にも、付き添いが必要な場合はその介助者にも移送費が支給されます。
また移送費の交通手段としては
- バス・電車などの公共交通機関
- タクシー
- 自家用車(1㎞あたり37円)
などが支給対象です。
ただし、タクシーは歩行が困難だったり、公共交通機関がなくやむを得ずタクシーを利用する場合に限られます。また、領収書の提出が必須条件です。
なお、高速代やパーキングの費用は支給対象外です。注意してください。
労災保険の移送費を申請する手順
労災保険の申請は労働基準監督署に対して行います。
提出する書類は「療養(補償)給付費用請求書」と「かかった費用の領収書」、「費用の内訳等明細書類」です。このうち療養(補償)給付費用請求書は会社、または厚生労働省のホームページからダウンロードできます。業務災害と通勤災害とでは用紙が異なりますので注意してください。なお、書類の名称が長いため通常は様式番号の5号、または16号の5の1などと言ったりします。
厚生労働省のホームページに掲載されている療養(補償)給付費用請求書記入例(書き方)では、(ヘ)移送費にて
- 家または職場から指定の病院までの片道・往復の距離
- 通った回数
- 通院費の総額
を記載しています。
なお、費用の内訳等明細書類には注意が必要です。この書類は労働局ごと又は労働基準監督署ごとに独自のフォーマットを用意していることがあります。また、書類の名称も異なることがあります。
書類の記入はもちろん準備する書類にも間違いがないよう、再度確認し、ミスのないようにしましょう。
労災保険で請求できる治療用装具費の種類や申請方法

労災保険で支給される治療用装具費には指定があり、医師による処方がなければ給付の対象とはなりません。
ここでは治療用装具費の種類と申請方法を解説していきます。
治療用装具として認められる装具には次のような例があります。
- 義肢(義手・義足)
- 義眼(保護に必要なモノ)
- 下肢装具
- 靴型装具
- 体幹装具
- 上肢装具
- 弾性着衣(ストッキング等)
- 膝サポーター
また、補助具としては
- 義眼
- 座位保持装置
- メガネ(条件あり)
- 補聴器(条件あり)
- 人工肛門受便器
- 盲人安全つえ
- 歩行補助つえ
- 車椅子
- 歩行器
などが認められています。
怪我の状況によって異なりますが、基本的には医師の判断によって給付の可否が決められます。
労災保険で請求できる治療用装具費の申請方法
労災保険の申請は移送費と同様に労働基準監督署に対して行います。
提出する書類は「療養(補償)給付費用請求書」と「かかった費用の領収書」、「費用の内訳等明細書類」です。このうち療養(補償)給付費用請求書は会社、または厚生労働省のホームページからダウンロードできます。業務災害と通勤災害とでは用紙が異なりますので注意してください。なお、書類の名称が長いため通常は様式番号の5号、または16号の5の1などと言ったりします。
治療用装具の給付を受け取るには、自費で費用を清算し、その後必要書類を提出する必要があります。また、治療用装具によっては手順が異なるため注意費が必要です。
申請の流れは次の通りです。
- 病院で診察を受ける
- 医師から装具作製業者(製作所等)に処方を出す
- 業者が装具を作製し。納品する
- 医師が装具の適合を確認し、医師から「意見書」と「装具装着証明書の原本」を受け取る
- 業者に装具費用を支払、「領収明細書の原本」を受け取る
- 会社を通して支給申請を行う
申請時に提出する書類は下記の6種類ですが、2から5は添付書類です。
- 様式第7号又は様式第16号の5(1)
- 医師の意見書
- 装具装着証明書の原本
- 領収明細書の原本
- 装具を全て写した写真
ただし、上記はコルセットやサポーターに関する申請の手順で、治療用の眼鏡・義眼・コンタクトレンズは
- 療養費支給申請書
- 医師の指示書の原本
- 患者の検査結果の原本
- 作製・購入時の領収書の原本
の添付書類が必要です。
医師の処方や指示書、領収書が必ず必要になるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ
労災保険では通院費と治療装具費も給付されます。建設業の一人親方は特に自分の身は自分で守らなければなりません。折角加入している労災保険の特別加入が無駄にならないためにも治療費がどの程度どの範囲まで給付対象となるのか万が一の労災事故に遭う前に確認しておくことは重要と言えましょう。
労働中の怪我や病気に対して支給される労災保険は、治療費そのものや休業中の給料の補填が重視されますが、それ以外にも通院にかかった費用と治療に使った装具の費用も給付される仕組みがあります。
通院が数回必要になって交通費がかかった場合、ギプスを装着するのに治療費としてギプス代が請求された場合など、治療のためにかかった費用は労災保険として支給されるか、必ず確認しましょう。
移送費および治療装具費には厳格な条件があるため、条件および提出書類にミスがないか、しっかり確認を行ってください。
一人親方の場合、雇用関係にある労働者と比較するとご自身でやるべきことが多くなります。不明な点は加入している一人親方団体に確認して、もれなく確実に書類を提出しましょう。