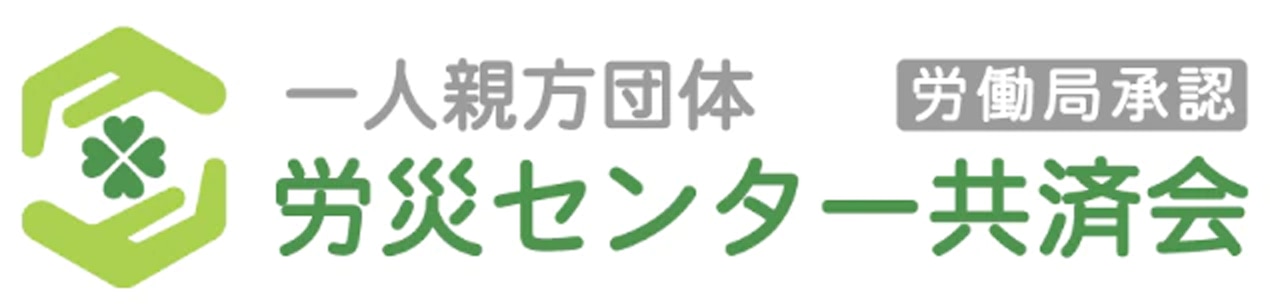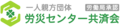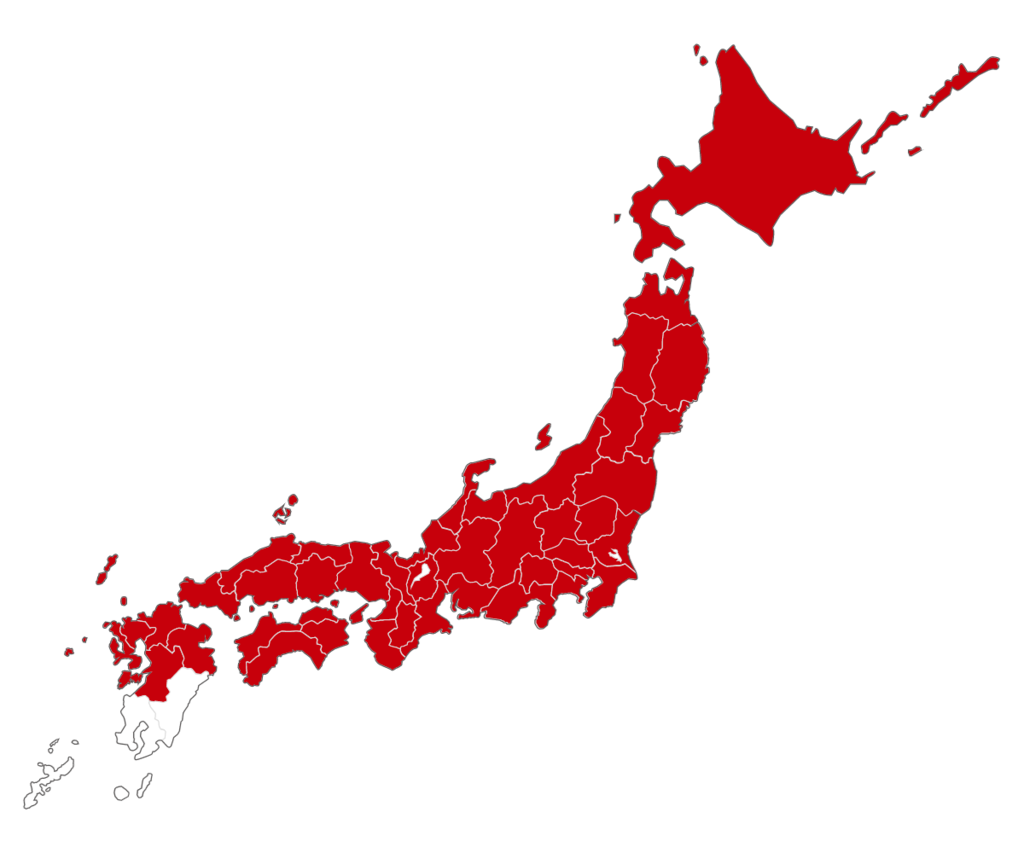労災保険と労働基準法の災害補償の関係についてわかりやすく解説します

労働中のケガや病気を支援する労災保険と労働基準法には密接な関係があります。労働基準法8章にある「災害補償」では一部、あるいは全額が会社に代わって負担されますが、これは労災保険の仕組みです。この記事では労災保険の給付項目と、労働基準法の「災害補償」の関係性を詳しく解説していきます。
なお、一人親方は自由意志により労災保険に特別に加入できますが、労働基準法は適用対象外です。とはいえ、労災事故が起きた場合に元請けとして被雇用者のみならず一人親方に対しても、一定程度損害賠償責任が生じることが多いと言えます。
目次[非表示]
- 1.労災保険と労働基準法の災害補償の違い
- 1.1.労災保険とは
- 1.2.労働基準法の災害補償とは
- 1.3.労災保険と労働基準法「災害補償」を比較する
- 2.労災保険と「使用者への損害賠償請求」の関係
- 3.まとめ
労災保険と労働基準法の災害補償の違い
まずは労災保険と労働基準法の災害補償、2つの内容を確認してみましょう。災害補償に関しては、労働基準法第8章・第75条~第88条で定められており、以下の災害補償があります。
ここでは
- 療養補償給付・療養給付
- 休業補償給付・休業給付
- 障害補償給付・障害給付
- 遺族補償給付・遺族給付
- 葬祭料・葬祭給付
- 傷病補償年金・傷病年金
- 介護補償給付・介護給付
- 二次健康診断等 給付
労災保険法と労働基準法の災害補償の比較の前に、労災保険法、労働基準法の災害補償の概要を見ていきます。
労災保険とは
労災保険の正式名称は労働者災害補償保険と言い、仕事中に発生した業務上でのケガや病気、あるいは通勤途上でのケガを補償するための国の制度です。
業務上で発生したケガや病気は「業務災害」、通勤途上でのケガを「通勤災害」と呼びます。労働災害とは業務災害と通勤災害を総称した呼称です。労災保険では労災の治療費や休まざるを得なくなった場合の給料を支援し、労働者の生活を守る役割があります。
労災保険は雇用形態に関係なく、アルバイト・パート・派遣でも、働いている方は必ず入らなければいけません。派遣の場合は派遣元の企業が労災保険料を支払い、出向の場合は指揮命令権がある会社が労災保険料を支払います。労災保険料はすべて会社負担です。
労災保険料は、従業員全員が貰っている給料の総額に労災保険率をかけて算出されます。労災保険率とは、職業ごと労災が起こる確率を反映して作られた数値で、労災が起きやすい仕事ほど労災保険料が高くなる仕組になっています。
労働基準法の災害補償とは

労働基準法第8章では「災害補償」について、使用者の災害補償責任が決められています。これは、労働上で発生した災害は全て会社(使用者)が責任を負うことを定めた法律で、労働災害として認められるものは全て会社が責任を負わなければなりません。
例えば従業員が機械の操作を誤ってケガをした場合、会社には過失がありませんが、就業時間中、業務に関する行為で発生したケガなので労働災害として認められ、労災保険が給付されます。
労災保険と労働基準法「災害補償」を比較する
労災保険では業務上または通勤中に負ったケガを治癒するために、「療養補償給付」や「療養給付」が支給されます。これにより、労災で負ったケガを治癒するための治療費はかかりません。労働基準法では「療養補償」で使用者側の療養費負担が明記されています。
労災で仕事を休んだ場合には「休業補償給付」「休業給付」が支給されます。支給は休業4日目から始まり、日当の8割が支給されます。労働基準法では「休業補償」で明記されています。
労災で負ったケガや病気で障害が残った場合、障害等級1級から第7級までに該当すると「障害(補償)給付」が支給されます。また障害のレベルに応じた年金のほかに、障害特別支給金という一時金が支給される場合もあります。労働基準法では「障害補償」で記載があります。
労災保険の中には、労災によって亡くなった従業員の遺族向けに「遺族(補償)給付」が支給されます。こちらも障害給付と同じく、年金と場合によって一時金が支給されます。労働基準法では「遺族補償」の項目で、遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならないと定めています。
葬祭にかかった費用も労災保険で支給されます。費用は315,000円に平均日当の30日分を加えた額です。労働基準法では「葬祭料」で、平均賃金の60日分の葬祭料を負担すると記載があります。
労災で負ったケガの中には、なかなか治癒が進まないものもあり、そういった場合には「傷病補償年金」「傷病年金」が支給されます。こちらは労働基準法には定めがありません。
労災によって負ったケガで介護が必要になった場合、労災保険では「介護保障給付」「介護給付」が支給されます。障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受け取っており、第1級と第2級の方で介護が必要な際に、104,970円を上限として支給されます。こちらも労働基準法には定めがありません。
また、労災保険では定期健康診断の結果で
- 血圧
- 血中脂質
- 血糖
- 肥満度
のすべてに異常が認められた場合は、二次健康診断や特定健康診断が給付として与えられます。労働基準法には記載がありません。
さらに、労働基準法の災害補償では「打切補償」という決まりがあり、療養期間が3年を超えても直らない場合は、使用者は平均賃金の1,200日分の「打切補償」を行えば、以降の補償は行わなくて良いとされています。これは労災保険には決まりがなく、打切補償は支給されません。したがって打切補償は会社が全額負担することになります。ただし、治療開始から3年経過した時点で傷病(補償)年金の支払いが続いている場合は、「打切補償をしたもの」とみなされます。
労災保険と「使用者への損害賠償請求」の関係

労災が発生すると、労災保険から治療費や休業中の給料などが補償されますが、会社に
- 安全配慮義務違反による労災
- 使用者責任による労災(ハラスメントや不注意の事故)
- 工作物責任による労災(足場の崩壊や漏電による火災など)
- 第三者行為災害による労災
が認められれば、会社側に損害賠償を請求できる可能性があります。
本来なら労災保険で適切な給付がされたとみなし、会社側には損害賠償の責任がなくなりますが、労災の原因があきらかに会社にある場合は損害賠償責任があります。
また、労災保険で補償されていない部分に関しては、企業が費用を負担しなければなりません。
さらに、労災保険料を会社が支払わなかった場合は、労災保険で支給された額の100%または40%を会社が負担します。もちろん時期をさかのぼって追徴するよう求められます。
労災保険では「損害賠償」の責任を免れない
労災保険は労働災害に見舞われた労働者の生活を守るだけでなく、治療費などを支払う企業助ける仕組みでもあります。労働基準法「災害補償」では労災時の補償について額面まで細かく記載がありますが、労災保険によって一部の負担を肩代わりしてもらえます。
ただし、労災の責任が全てなくなるわけではありません。会社側の行動で労災が起こってしまった場合は、従業員に対して損害賠償を行う責任が伴います。普段から安全確認や職場環境の整備を徹底し、労災が起きないように心がけるのが大切です。
まとめ
労災保険は労働基準法「災害補償」を肩代わりするものです。また、法人であっても個人であっても災害補償の責任は事業主にあります。特に建設業であれば労働災害は避けて通れません。労災保険の手続きをきちんとして、従業員の生活や会社を守りましょう。
今回は労災保険と労働基準法の災害補償との関係性をご説明しました。労働者災害補償保険法は企業の事情によって災害補償が履行されない状況を反映し、昭和22年に制定された法律です。
事業主は労災保険に加入することで、従業員は確実に給付を受けることができ、企業も状況に左右されずに確実に補償を行えます。滞納や未加入が起こらないように、再度確認を行いましょう。