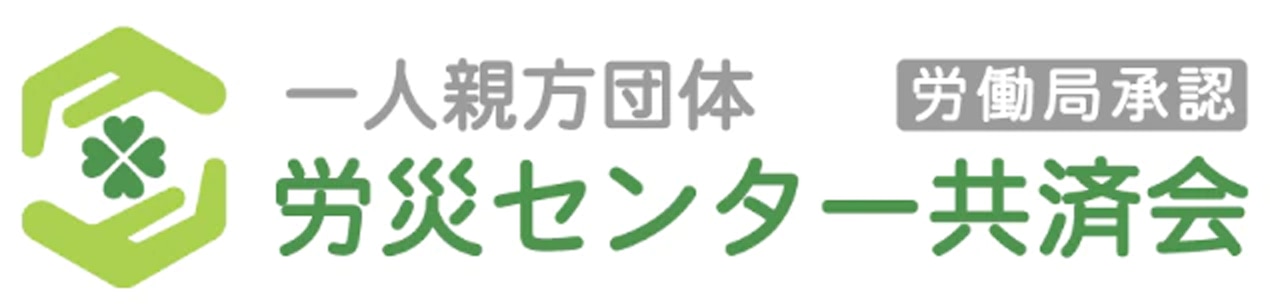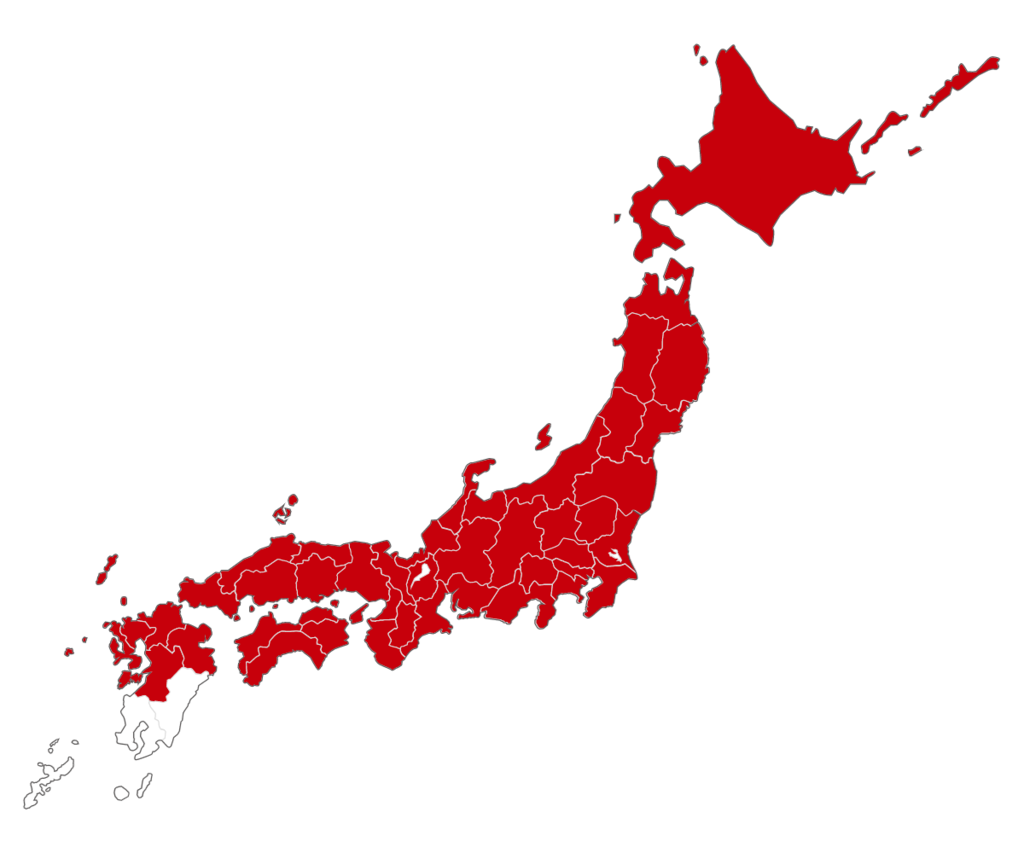一人親方なら知っておくべきフリーランス新法とは?対象者・対象となる取引・課される義務などを徹底解説
令和6年11月1日(2024年11月1日)より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が施行されます。フリーランス新法は、フリーランスが安定して働ける環境を整え保護するために、フリーランスへ業務を委託する事業者に対してさまざまな義務を課すものです。
この記事では、フリーランス新法の概要や発注事業者に課せられる義務、違反した際の罰則、一人親方が特に注意すべきポイントを解説します。「フリーランス保護新法」とも呼ばれるフリーランス新法の内容を理解し、法律に則って業務を行なえるよう準備を進めましょう
目次[非表示]
- 1.フリーランスを守る「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
- 2.フリーランス新法の対象者・対象となる取引
- 2.1.フリーランス新法の対象者
- 2.2.フリーランス新法の対象となる取引
- 3.フリーランス新法で発注者に課される7つの義務
- 3.1.①書面等による取引条件の明示
- 3.2.②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 3.3.③1ヵ月以上の業務委託をした場合の禁止行為の追加
- 3.4.④募集情報の的確表示
- 3.5.⑤育児や介護などと業務の両立に対する配慮
- 3.6.⑥ハラスメント対策の体制整備
- 3.7.⑦中途解約等の事前予告・理由開示
- 4.フリーランス新法による罰則
- 5.フリーランス新法施行で一人親方が注意したいポイント
- 6.まとめ
フリーランスを守る「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
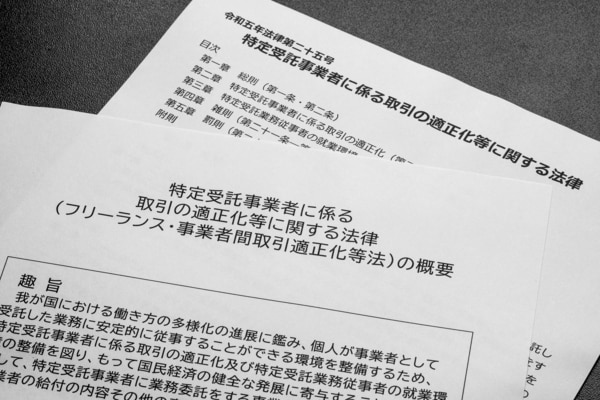
働き方の多様化が進むなか、フリーランスが増えつつある一方で、報酬の不払い問題やハラスメントなど、取引先とのトラブルが発生しています。こうしたトラブルを解消し、フリーランスが安心して働ける環境を整え保護するために設けられたのが、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)です。
目的は大きく2つあり、1つは「取引の適正化」、もう1つは「就業環境の整備」です。これらを達成するために、法律ではフリーランスと契約する発注事業者に対してさまざまな義務を課しています。
また、個人事業主の一形態である建設業などの一人親方も、フリーランス新法の対象となります。法律は、令和6年(2024年)11月1日から施行されるため、事前に概要を知っておくことが大切です。
フリーランス新法の対象者・対象となる取引

フリーランス新法の具体的な内容に入る前に、まずはこの法律の対象となる人や取引について解説します。
フリーランス新法の対象者
フリーランス新法の対象者は、以下の条件を満たすフリーランスおよび発注事業者です。
- フリーランス(特定受託事業者)
次の1または2に該当する個人または法人が対象です。
- 従業員を雇っていない個人
- 代表者1名のみで、役員や従業員がいない法人
※副業としてフリーランスをしている場合も含まれます。
- 発注事業者
発注事業者には、「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」があります。
特定業務委託事業者:①従業員を雇っている個人、または②役員や従業員がいる法人
業務委託事業者:フリーランスに業務を委託するすべての事業者(フリーランスを含む)
なお、フリーランスのような下請事業者を守り、発注事業者の濫用行為を取り締まる法律には「下請法」があります。フリーランス新法は下請法とは異なり、業種や資本金の大小を問わず適用される点が特徴です。
フリーランス新法の対象となる取引
フリーランス新法の対象となるのは、事業者からフリーランスへの業務委託です。具体的には、物品の製造・加工委託、情報成果物の作成委託、役務の提供などが該当し、業種・業界を問わず、すべての業務が適用対象となります。また、仲介事業者がフリーランスに対して再委託している場合も法律の適用を受けます。
ただし、実質的に労働基準法の労働者と判断される場合や、単なる商品の販売行為は法律の適用外です。
フリーランス新法で発注者に課される7つの義務
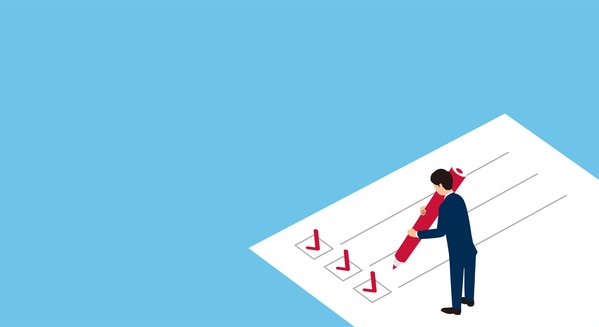
フリーランス新法では、発注事業者に以下の7つの義務が課されています。
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
- 1ヵ月以上の業務委託をした場合の禁止行為の追加
- 募集情報の的確表示
- 育児や介護などと業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策の体制整備
- 中途解約等の事前予告・理由開示
ただし、すべての発注事業者が7つの義務すべてを負うわけではありません。発注事業者の種類や状況に応じて、以下のとおり満たすべき義務が異なります。
発注事業者の要件 |
満たすべき義務 |
||
|---|---|---|---|
従業員を使用していない場合 |
義務項目① |
||
従業員を使用している場合 |
義務項目①②④⑥ |
||
従業員を使用しており一定期間 以上の業務委託を行なう場合 |
1ヵ月以上の業務委託の場合 |
義務項目①②③④⑥ |
|
6ヵ月以上の業務委託の場合 |
義務項目すべて |
||
7つの義務の内容をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①書面等による取引条件の明示
業務委託を行なう際は、取引条件を書面または電磁的方法により明示しなければなりません。口頭での確認は認められておらず、電磁的方法には電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなどが含まれます。
明示すべき取引条件は、以下の8項目です。
- 業務委託事業者および特定受託事業者の名称
- 業務委託を行なった日
- 特定委託事業者の給付の内容
- 給付を受領または役務の提供を受ける期日
- 給付を受領または役務の提供を受ける場所
- 給付内容について検査する場合は、検査を完了する期日
- 報酬額および支払期日
- 現金以外で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
特に一人親方は、口頭で仕事を請け負う場合が多い傾向にあります。実際に、労災事故対応の際、一人親方に対して請負契約書などの提示を求めると、書面ではなく口頭で契約が成立したという回答は少なくありません。トラブルを避けるためにも、取引条件は必ず書面で確認するようにしましょう。
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。
支払期日を定めなかった場合は、物品等を受領した日が自動的に支払期日となります。また、給付を受領した日から起算して60日を超えて支払期日を定めた場合、60日が経過した日が支払期日となります。
③1ヵ月以上の業務委託をした場合の禁止行為の追加
発注事業者がフリーランスと1ヵ月以上の業務委託を行なう場合、以下の7つの禁止行為が定められています。
禁止行為 |
内容 |
|---|---|
⦁ 受領拒否 |
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受け取りを拒むこと。 |
⦁ 報酬の減額 |
フリーランスに責任がないのに、契約時に定めた報酬額をあとから減額すること。 |
⦁ 返品 |
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせること。 |
⦁ 買いたたき |
通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を定めること。買いたたきかどうかは、報酬額を決定する際にフリーランスとの十分な協議がされていたか、対価の決定内容は適正かなどで判断されます。 |
⦁ 購入・利用強制 |
正当な理由なく、発注事業者が指定する物品や役務の購入や利用を強制すること。発注事業者に強制の認識がなくても、事実上の強制があれば規制対象となります。 |
⦁ 不当な経済上の利益の提供要請 |
発注事業者が自身の利益のために、フリーランスに金銭や役務、その他の経済上の利益を提供させること。 |
⦁ 不当な給付内容の変更・やり直し |
フリーランスに責任がないのに、費用を負担させて給付内容を変更させたり、受領後に給付をやり直させたりすること。 |
④募集情報の的確表示
広告などでフリーランスを募集する際、発注事業者は情報に対して以下の3つの義務を負います
- 虚偽表示の禁止
- 誤解を生じさせる表示の禁止
- 正確かつ最新の表示の義務
⑤育児や介護などと業務の両立に対する配慮
6ヵ月以上の期間で業務委託を行なう場合、発注事業者は育児や介護などと業務を両立できるよう配慮しなければなりません。6ヵ月未満の委託の場合は、配慮するように努める努力義務があります。
フリーランスから育児や介護などの配慮を求められた場合、発注事業者はその申出の内容を把握し、可能な対応策を十分に検討する必要があります。検討結果はフリーランスに伝達し、配慮が実施できない場合はその理由を説明しなければなりません。
⑥ハラスメント対策の体制整備
セクシュアルハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産に関するハラスメント(マタハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)など、各種ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害さないよう、発注事業者は必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、ハラスメントに関する方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するための体制整備、ハラスメントが発生した場合の迅速な対応が求められます。また、フリーランスがハラスメントについて相談したことを理由に、不利益な扱いをするのも禁止されています。
⑦中途解約等の事前予告・理由開示
6ヵ月以上の業務委託契約の際、発注事業者が契約の解除または更新しない場合は、例外的な事由がない限り、解除日または契約満了日の30日前までにフリーランスにその旨を予告しなければなりません。
ただし、災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合や、フリーランスに責任がある場合には、予告が不要となります。
フリーランス新法による罰則

フリーランス新法に違反があった場合、フリーランスは各機関の窓口にその旨を申し出ることが可能です。行政機関は申出内容に応じて調査を行ない、その結果に基づいて指導や助言、勧告を行ないます。
発注事業者が行政機関の勧告に従わない場合、命令・公表が行なわれ、さらに命令に違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
フリーランス新法施行で一人親方が注意したいポイント

フリーランス新法施行にあたり、一人親方が注意すべきポイントを2つ解説します。
フリーランスからフリーランスへの業務委託も法律の対象
フリーランス新法は、受託事業者と発注事業者の両方がフリーランスである場合にも適用されます。自身が発注者としてフリーランスに業務を依頼する場合は、法律の要件を満たせるよう体制を整備しておく必要があります。
フリーランスへの発注を予定している方は、特定受託事業者および発注事業者の両方の視点から、フリーランス新法の内容を確認しておきましょう。
違反行為は申し出なければならない
フリーランス新法に違反する行為があった場合、担当省庁への申出が必要です。申出がないと対応してもらえないため注意しましょう。また、申出先の行政機関は違反内容によって異なるため、正しい機関に申出を行なうことが重要です。
公正取引委員会・中小企業庁 |
厚生労働省 |
|---|---|
|
|
違反行為かどうか判別できない場合は、「フリーランス・トラブル110番」に相談するのがおすすめです。ここでは、取引上のトラブルを弁護士にワンストップで相談できるサポートを提供しています。
フリーランス・トラブル110番
https://freelance110.mhlw.go.jp/
まとめ
令和6年(2024年)11月1日に施行されるフリーランス新法(フリーランス保護新法)は、フリーランスが安定して働ける環境を整えるための重要な法律です。この新法は、フリーランスとその発注事業者との間の取引の適正化や就業環境の改善を目的とし、発注事業者に対してさまざまな義務を課しています。
フリーランスとして働く方や、フリーランスに業務を発注する予定の方は、法律の内容をよく理解したうえで、適切に対応できるよう準備を整えておきましょう。