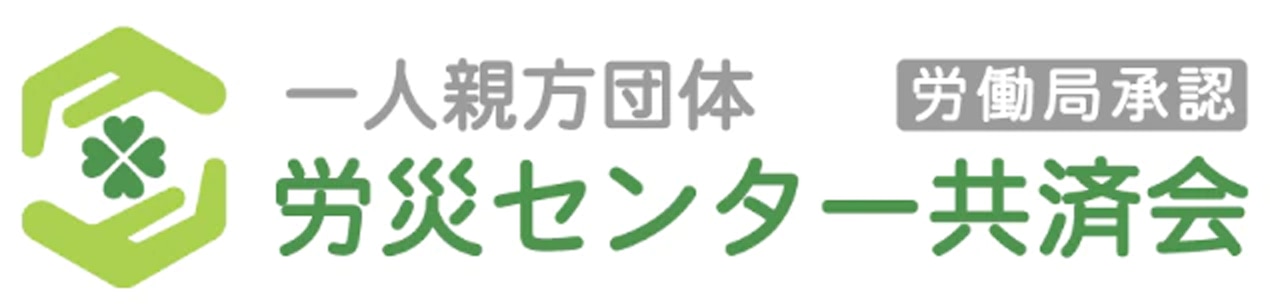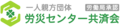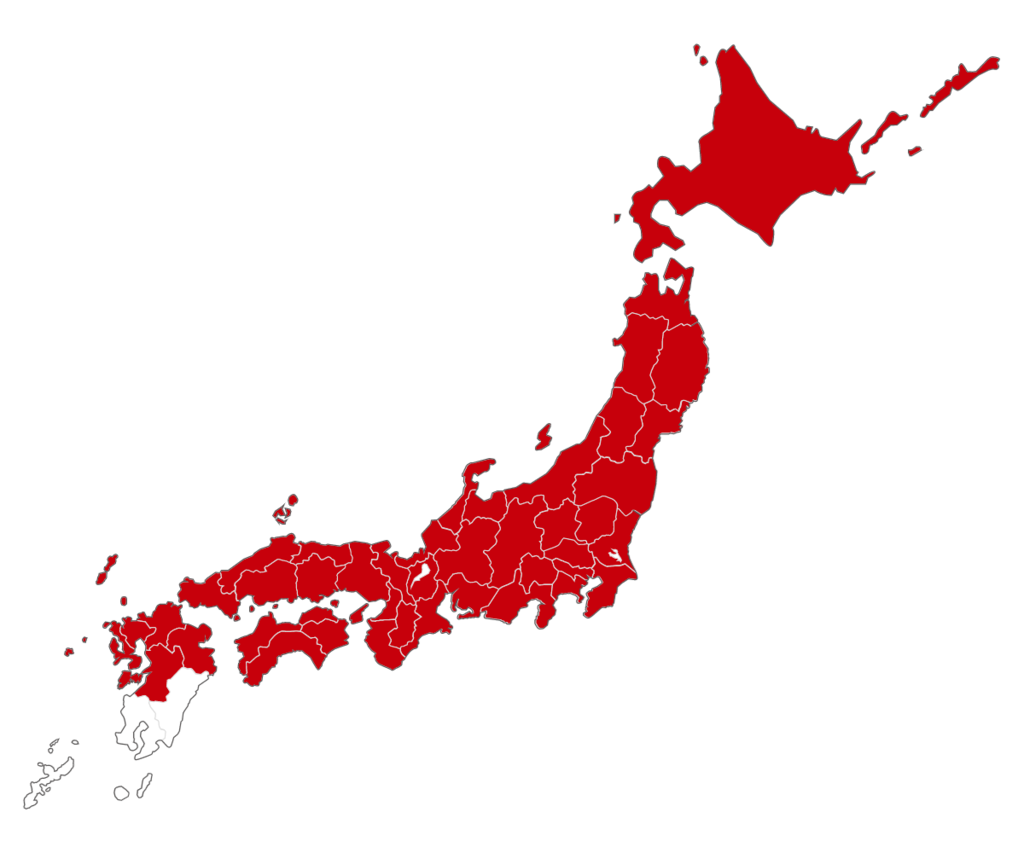労災の給付申請には期限がある!保険給付における種類ごとの時効・起算日も解説

あらゆる労働者にとって「労災」は大切な制度です。特に、建設現場などで働く一人親方のような人の場合、事故に巻き込まれるリスクが高いため、申請する可能性は高いでしょう。
しかし、労災の給付申請には期限があります。その期限内に必要な手続きを済ませなければ、給付金を受け取れない状況に陥ってしまうかもしれません。
この記事では、労災保険給付における時効・起算日を種類ごとに解説しつつ、申請期限が過ぎたときの対処法も紹介します。
目次[非表示]
- 1.【種類別】労災申請における期限と時効
- 1.1.療養(補償)給付
- 1.2.休業(補償)給付
- 1.3.遺族(補償)年金
- 1.4.遺族(補償)一時金
- 1.5.葬祭料(葬祭給付)
- 1.6.未支給の保険給付・特別支給金
- 1.7.傷病(補償)年金
- 1.8.障害(補償)給付
- 1.9.介護(補償)給付
- 1.10.二次健康診断等給付金
- 2.うつ病とアスベスト健康被害で労災申請する場合
- 3.申請期限が過ぎた場合の対処法
- 4.まとめ
【種類別】労災申請における期限と時効

労災保険給付には、多くの種類があります。労災申請における期限や時効のルールは種類によって異なるので、注意しましょう。
なお、労災申請の期限について調べる場合には、労災の時効起算日となる「請求権の発生日」と、労災の申請期限となる「時効が完成する日」の2つを押さえること必要です。
また、労災申請における「時効」とは、労災の申請手続きを長期間行なわなかったときに、労災給付金の受給権利がなくなってしまう期限を指します。
ここでは、労災における各給付の概要を踏まえつつ、請求権の発生日と時効(申請期限)について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
療養(補償)給付
仕事(業務または通勤)が原因の傷病により、療養を受けるときの労災給付です。
労災病院もしくは労災保険指定医療機関・薬局などで治療を受けたり、薬を処方してもらったりした場合、窓口での自己負担がなく無料となります。そのため、労災の申請期限もありません。
一方、上記に該当しない医療機関を受診した場合、療養費はいったん自分で立て替えるため、その自己負担分の請求に対してルールが適用されます。起算日の期限は療養費を支払った日の翌日、時効はその翌日から2年が期限になります。 なお、定期的に通院している場合、労災の請求権が毎回発生します。時効の期限も療養費の支出日ごとに期限は2年と設定されるので、請求権が発生するタイミングと請求期限を併せて覚えておきましょう。
休業(補償)給付
仕事(業務または通勤)が原因の傷病でしばらく療養するために労働できず、賃金を受け取れないときに申請できる労災給付です。 労災の期限は賃金を受け取らなかった日の翌日から起算し、期限は2年となりその時点で時効完成となります。
遺族(補償)年金
仕事(業務または通勤)が原因の傷病によって被災労働者が死亡したとき、一定の条件を満たしている遺族が申請できる労災給付です。 労災の期限は被災労働者が死亡した日の翌日から5年経過すると、時効が完成します。
遺族(補償)一時金
こちらも仕事(業務または通勤)が原因の傷病によって被災労働者が死亡したときの労災給付ですが、遺族年金の対象となる遺族がいないときに申請できます。
遺族(補償)年金と同じく、労災の期限は被災労働者が死亡した日の翌日から起算し、期限は5年で時効完成となります。
葬祭料(葬祭給付)
仕事(業務または通勤)が原因の傷病によって被災労働者が死亡し、葬祭を行なうときに申請できる労災給付です。
原則として、葬祭を執り行なう遺族に労災が給付されますが、遺族がいないといった事情から社葬で送り出した場合は、行なった会社が給付対象となるケースもあります。 労災の期限は被災労働者が死亡した日の翌日、時効となる期限はその翌日から2年となります。
未支給の保険給付・特別支給金
療養(補償)給付や休業(補償)給付などを支払うべき被災労働者が受給前に死亡したとき、その遺族は未支給分を申請手続きすることが可能です。未支給分とは、以下のような保険給付を指します。
- l 労災の請求権は発生しているが、申請が行なわれていないもの
- l 労災の申請は行なわれているが、支給が決定されていないもの
- l 労災の支給は決定しているが、まだ支払われていないもの
起算日や時効はそれぞれの保険給付と同じになるため、タイミングや期限をしっかりと確認しましょう。
傷病(補償)年金
仕事(業務または通勤)が原因の傷病を負って、療養を開始してから1年6ヵ月経っても治らず、障害の程度が傷病等級に当てはまるときの労災給付です。
他の労災給付と違って被災労働者に請求権は発生せず、労働基準監督署長の職権に基づいて支給決定の判断が下されます。労働者から申請できるものではないため、こちらも申請期限はありません。
また、期限の定めはなく療養が続いている限り、給付も継続されるので期限を気にしなくても問題ないです。
障害(補償)給付
仕事(業務または通勤)が原因の傷病が症状固定したものの、障害等級に当てはまる身体障害が残ったときの労災給付です。 傷病が治癒した日の翌日から起算して、5年で時効期限を迎えます。“治癒”とは「治療を継続しても、それ以上回復する見込みがない状態」を指すので、起算日や期限を押さえておきましょう。
介護(補償)給付
傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給していて、一定の傷病等級・障害等級に該当し、なおかつ現在介護を受けている場合に申請できる労災給付です。常時介護と随時介護の違いによって、上限金額も変わってきます。 介護を受けた月の翌月1日から起算して、時効となる期限は2年です。ただし、月単位で支給されるため、毎月介護を受けているなら起算日ごとに時効が発生しますので期限には注意しましょう。
二次健康診断等給付金
労働安全衛生法に基づく一次健康診断を受けて、以下の検査項目すべてに異常の所見があると診断された場合、二次健康診断や特定保健指導を年1回無料で受けられる労災給付です。
- 血圧
- 血中脂質
- 血糖
- 腹囲もしくは肥満度(BMI)
一次健康診断の受診日から3ヵ月が時効期限ですが、申請ではなく受診しないときに権利失効となるため、期限には注意しておきましょう。
うつ病とアスベスト健康被害で労災申請する場合

うつ病もしくはアスベスト(石綿)による健康被害で労災申請をする場合、他の傷病と比べて手続きのタイミングや申請期限に違いがあります。
以下に注意すべきポイントをまとめたので、こちらも併せて確認してください。
うつ病で労災申請する場合の期限
うつ病は精神的な疾患ですが、仕事によるストレスなどが発症原因であれば、労災からの補償は認定されます。
実際のところ、うつ病による労災受給が認定された割合は30%前後とは高くありません。しかし、それでも労災が認定されれば、健康保険の傷病手当金よりも手厚い保証が受けられるため、認定されるかわからなくても申請を提出するとよいでしょう。
ただし、うつ病が労災として認定されるためには、仕事との因果関係をきちんと証明しなければなりません。申請内容に対して「仕事と私生活のどちらに起因するものなのか」を慎重に判断する必要があるため、身体的な病気や怪我と比べて時間がかかってしまいます。
また、うつ病であっても、申請期限や時効は他の傷病と変わりませんが、認定までに時間がかかることを踏まえれば、余裕を持って申請したほうがよいでしょう。業務による心身の不調を少しでも感じたら、早めに医師の診察を受けてください。
なお、うつ病は身体的な傷病と比べて認定ハードルが高いため、健康保険の傷病手当金をまず申請したうえで、労災申請を行なう方法が一般的です。
アスベスト(石綿)による健康被害があるときの期限
アスベスト(石綿)とは、ビニール床のタイルや建築材料の製造に使われてきた素材です。これを業務中に吸引した場合、肺がんや中皮腫といった病気を引き起こす危険性があります。
実際、アスベストによる健康被害を受けた労働者は数多く、国に対して損害賠償を求める訴訟も行なわれてきました。そして、2006年9月には、アスベストを含有する建築材料などの製造・使用が全面禁止となっています。
アスベストによる健康被害で注目すべきポイントは、吸引から長い期間を経て発症するのが一般的であることです。かつては被災労働者が病気を発症しても、時効の問題から労災として認められず、亡くなった場合においても遺族(補償)給付を受けられないというケースが多発していました。
このように被災労働者を亡くしたうえ、5年間の時効によって受給権利まで消滅した遺族に対し、特別な救済措置として支給されているものが「特別遺族給付金」です。特別遺族給付金は制度改正を通じて、申請期限が2022年3月27日まで延長されています。特別遺族給付金の申請を行なう方は注意しましょう。
申請期限が過ぎた場合の対処法

労災における各給付の時効(申請期限)が過ぎてしまっても、すぐ諦めてはいけません。状況によっては補償を受けたり、金銭請求を行なったりすることができます。
代表的なケースと対処法を以下にまとめたので、見ていきましょう。
治療を受けたり休んだりした日から考える
療養・休業・介護給付の場合、以下のように日(月)ごとに時効が進行するので、タイミングによっては申請できる可能性があります。
- 療養(補償)給付:労災保険指定医療機関以外で治療を受けた日・薬をもらった日
- 休業(補償)給付:療養するために労働できず賃金を受け取れなくなった日
- 介護(補償)給付:介護を受けた月の翌月1日
「2年以上前に負った怪我だから、労災の申請期限はとっくに過ぎてしまっている」などと思っていても、諦めるのは早計です。病院で治療を受けたり、療養のために会社を休んだりした時期が2年以内に収まっているかもしれません。
労災申請はなるべく早めに書類を手配し手続きを済ませるのが理想ですが、療養に専念して申請を忘れてしまったり、時効のタイミングを勘違いしたりする可能性もあります。
そのため、申請期限が過ぎたと感じても、まずは落ち着いて各給付の起算日を確認することが大切です。自分だけで解決できない場合には、レセプトなどの書類を用意し労働基準監督署や社労士などにも相談してみましょう。
安全配慮義務違反で金銭請求できることもある
労災保険の存在をよく知らなかったり、悪質な会社がパワハラや労災隠しなどで労働者からの申請を妨げたりした結果、申請期限を過ぎてしまうケースがあります。
そして、法律に基づく請求権が失効すると、原則として労災申請を行なうことはできません。労働基準法75条以降では、従業員が業務中または通勤途上で何らかの傷病を負った場合、会社はそれを補償する責任があると定めています。
しかし、労働被災者がすでに労災保険から補償を受けていれば、その範囲内において会社側の責任は免除されることが、労働基準法第84条1項に定められているのです。
また、労働契約法第5条では、会社は従業員に対して「安全配慮義務」を負うと定められています。もし、会社側が安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任による不法行為が認定された場合、以下の期限内で損害賠償を請求することが可能です。
- 債務不履行:5年
- 不法行為:5年
なお、民法改正前(2020年3月31日以前)の事案については、期限が変わる可能性もあるため、証拠などを専門家に提出し相談してみましょう。
まとめ
労災保険給付はたくさんの種類に分かれており、それぞれ申請期限が異なっています。すべて細部まで把握するのは難しいかもしれませんが、特別な場合を除き2年もしくは5年で受給権利が失効することは最低限覚えておきましょう。
また、うつ病やアスベストによる健康被害など、傷病によっては労災認定までに時間がかかったり、特例が適用されていたりするため、その辺りも押さえておく必要があります。
建設現場など事故のリスクが高い場所で働くなら、労災に対する理解も深めておきましょう。