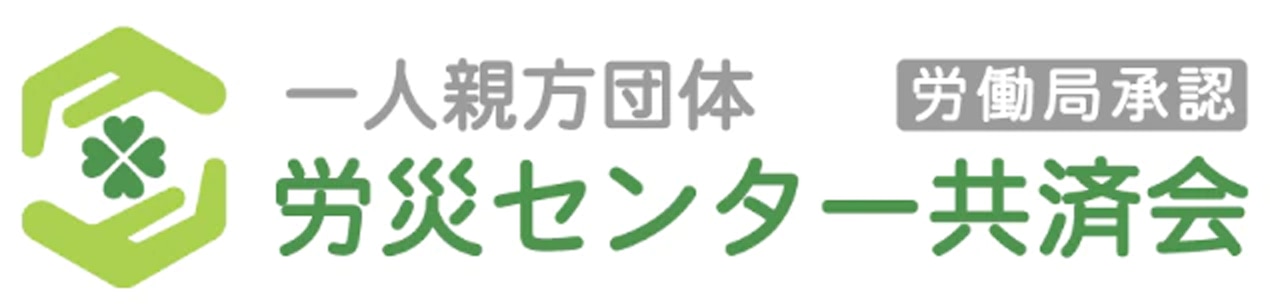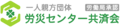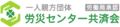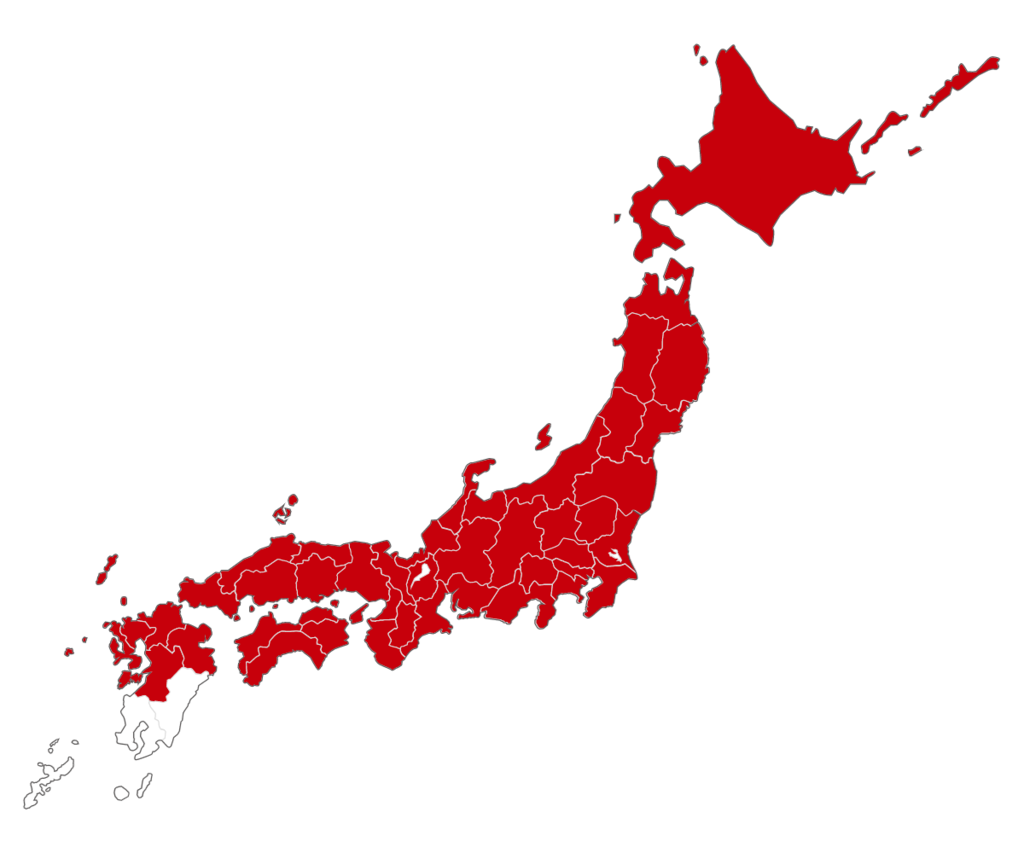一人親方の年収はどれくらい?安定した収入を得るために気を付けることは?

一人親方としての独立を考えている方にとって、どのくらいの収入が得られるのかは非常に重要な問題です。また、収入額にもまして重要なことは、安定して収入が得られるか否か、という点です。
一人親方の年収は職種や働き方によって大きく異なり、不安定であることも珍しくありません。しかし、基本的なポイントを理解すれば収入を安定させることができ、年収をあげられる可能性も高まります。また、万が一の事態に備え、保険を知っておくことでより安定的に働きやすくなります。
そこでこの記事では、一人親方の収入について詳しく解説し、年収をあげる方法や保険に関することにも言及しています。
目次[非表示]
- 1.一人親方とは何か?
- 2.一人親方の年収はどれくらいか?
- 3.年収1000万円は可能?年収をあげる方法
- 3.1.職種の変更や資格の取得
- 3.2.人とのつながりを大切にする
- 3.3.節約、節税を心掛ける
- 4.安定した収入を得るために保険に入ろう
- 4.1.万が一の事態に備えよう
- 4.2.選ばれる労災保険の特徴
- 5.まとめ
一人親方とは何か?

一人親方とは個人事業主の一種であり、おもに建設業などで労働者を雇用せずに事業を行なう事業主のことを指します。例えば一人親方には以下のような職種があります。
- 土木、建築、その他の工作物の建設や改造、修理などに携わる職業・・・大工職人、左官職人、とび職人など
- 除染を目的として高圧水による高作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などを行なう事業者
- 林業に従事する職人
- タクシー運転手
一人親方は確定申告や社会保険などの加入は行なう必要がありますが、会社員として働く場合に比べて自由な仕事の取り方ができますし、受注の仕方によっては年収を大きくアップさせることも可能です。
また、一人親方として建設の事業に従事する場合、一定要件を満たし“一人親方等”として認められることで個人事業主でありながら労災保険の適用を受けることもできます。一人親方以外の労働者を雇用していないことが前提ですが、家族だけで業務を行なっている場合や、雇用していたとしても年間の雇用日数が延べ99日以下であれば、一人親方として認められます。
例えば、一人親方以外にアルバイトを2人雇用した場合、2人の出勤日数の合計が99日以下であれば問題ありません。通常の個人事業主では本来加入できないものですが、特別加入制度によってこれが認められています。
つまり、建設業などの特定の業種を担う事業者は、一人親方として個人事業主のメリットも受けつつ、法人のように労災保険の補償も受けられるのです。
一人親方の年収はどれくらいか?
一人親方として仕事をしようと考えている方にとって、どれだけの収入が得られるのかはとても気になることでしょう。ただし、一人親方は地域や職種、仕事の受け方によって年収の目安が大きく異なります。
厚生労働省が発表している統計における、建設業の会社員は平均年収333.2万円とされています。一人親方の年収は後述するように職種によって大きく異なりますが、安定的に仕事を受注できれば、会社員より一人親方の方が高い給料を受け取れる傾向にあります。
ただし、一人親方の年収に関しては、以下の点に注意しなくてはなりません。
- 開業資金と経費
会社員の場合は会社側で作業道具や消耗品を準備してくれますが、一人親方はご自身で用意しなくてはなりません。開業資金として最低でも50~100万円は必要になるでしょう。日常の仕事においても、材料費や設備費、車のガソリン代などがご自身の負担となることを理解しておきましょう。
- 収入の幅
一人親方の収入は基本的に単価×受注数となるため、固定給の会社員と比較すると年収の幅が広くなりやすいです。継続的に案件が受注できれば会社員よりも高収入になりますが、仕事が得られなければ会社員以下の収入になってしまうリスクもあります。
上記をふまえて、業種ごとの平均年収をチェックしていきましょう。
造園の年収
造園業を営む一人親方の平均年収は、約700万円から800万円です。
一方、造園業全体の平均年収は、約300万円~450万円です。20代(月収17万円~20万円)、30代(20万円~25万円)、40代(25万円~30万円)と年齢に比例して平均収入は増加します。
いずれの年代においても、会社員としての平均年収よりも一人親方の方が高収入を得やすいでしょう。
内装業の年収
内装業は、住居のリフォームやリノベーション、修復の際の内装工事を請け負う業種です。近年のリノベーションブームもあり、非常に人気が高まっています。
内装業の一人親方の平均年収は、約600万円です。内装業は、初期投資が少なく済むため、一人親方として独立しやすいというメリットもあります。
配管工の年収
ガスや配管設備を担当する配管工一人親方の平均年収は、550万円~700万円です。配管工は、住宅のリフォームや新築において需要が高いため、一人でも独立しやすい仕事です。
電気工事士の年収
一人親方の電気工事士の平均年収は、500~600万円です。他の業種と同様、会社員として働くよりも高収入を得るチャンスがあります。
電気工事士の仕事のなかでも特に高単価な仕事は、エアコンの取り付けや取り外しです。1件あたり、10,000~15,000円程度の単価が期待できるため、一日に3件4件と案件を担当すればかなりの収入になります。しかし一方で、シーズンによって収入にバラツキが生じやすい点に注意が必要です。
大工の年収
一人親方の大工の平均平均は、約900万円です。一人親方は、工事施工業者から「元請け」として仕事を受注できるため、得られる収入は多くなります。
溶接工の年収
一人親方の溶接工の平均年収は、約700万円です。人によっては1000万を超えることもあります。ただし、高収入を得るためには相応の経験が必要です。また、溶接の資格を取ることも大事です。最初はアーク溶接作業者資格やガス溶接作業者資格を取り、その後は自身のキャリアプランに応じてその他仕事に関連する資格を取得する必要があります。
年収1000万円は可能?年収をあげる方法
一人親方の年収には幅が生じやすいですが、その幅は運に左右されるものではありません。働き方を工夫したり、対策をしたりすることで、収入を増やせる可能性は高められます。
以下では、一人親方が高収入を得るための3つのコツを紹介します。
職種の変更や資格の取得
一人親方は、職種や担当する仕事内容によって案件単価や仕事のニーズが異なります。したがって、ニーズの多さや平均単価を調査したうえで、単価のよい職種に変更すれば、高収入を得やすくなります。
また、一つの職種しか担当できない一人親方よりも複数の業種を担当できる一人親方の方が、仕事を得るチャンスも1件の仕事あたりの単価も増やせます。例えば、内装の仕事に加えて塗装の仕事を担当できるようになれば、リフォームの際に一人で内装と外壁塗装の両方を担当可能となり、一つの案件で発生する報酬を増やすことができます。
このように仕事の幅を広げるためには資格の取得も有効です。資格を持っていると、対外的に自らの知識やスキルが一定水準以上にあることを示しやすくなります。
調査の結果、収入が多く得られそうと思われる領域で役立つ資格取得を目指すとよいでしょう。
人とのつながりを大切にする
一人親方が、案件を受注するために大切なことは人とのつながりです。例えば、元請会社の担当者と信頼関係が築ければ、それだけでも優先的に仕事を貰いやすくなります。元々人脈がないという方は、協力業者を募集している請負元に対して自らアプローチするなどの対策も効果的です。
節約、節税を心掛ける
せっかく収入が増えても、それだけ経費や税金による支出も増えてしまっては収益も増加しません。そこで以下のポイントを押さえて経費の節約や、節税に取りかかりましょう。実際、節約や節税を心掛けると、手元に残るお金がまったく違ってきます。
- 備品や消耗品を購入する際、費用対効果を考慮しつつ低コストのものを選ぶようにする
- 備品代や消耗品代、交通費など、経費として計上できるものを漏れなく申告して課税額を抑える
- 確定申告の際に、控除できる項目を把握し、一つひとつ正確に申告をする(生命保険、労災保険、外注費用など)
確定申告は難しいというイメージを持つ方も多いと思いますが、会計ソフトを使用すれば比較的簡単に管理できます。
安定した収入を得るために保険に入ろう

一人親方が安定した年収を得るためには、万が一の事態に備えることも重要です。一人親方が特別に加入できる保険の制度がありますので、これを有効活用し、活動が継続できるようにしましょう。
万が一の事態に備えよう
一人親方は、業務上のケガのリスクがあります。例えば、屋根や足場にのぼって作業をする大工は、落下してケガをしてしまう危険性があります。
そして一人親方は会社員のように基本給が補償されていないため、ケガによってしばらく働けなくなると収入が途絶えてしまいます。このようなケースでの保障として利用したいのが、一人親方労災保険です。
労災保険は、本来会社員でなければ加入できませんが、ケガのリスクが高い建設業では特別に加入が認められています。建設業で従事する一人親方が保険に加入していることで、業務上のケガを負っても治療費の自己負担が0円になったり、基礎給付日額に応じたお金を受け取れたりするなどの補償が整っています。
選ばれる労災保険の特徴
一人親方労災保険は、労働局が承認した団体を通じて加入しなくてはなりません。そして、団体の選び方によって一人親方労災保険の安心感や満足度は大きく変わります。
一人親方労災保険の団体を選ぶ際に重視したいのは、以下の3点です。
- 金額の安さ
一人親方労災保険に加入すると、保険料と団体に支払う手数料を負担することになります。保険料率は法令で決定されているため、どの団体から申し込みをしても一律ですが、団体に支払う組合費や入会金、手数料などは団体によって異なります。そのため金額の安さを重視するならこれら各種費用の安い業者を選んで、支払い総額を抑えましょう。
- 丁寧な対応
いざケガをしてしまうと、どのように保険を受け取ればよいのかがわからずパニックになりがちです。そのためどのような状況でも丁寧に対応してもらえる団体であるほうがよいでしょう。本人も落ち着いて受け答えしやすくなります。また、丁寧に対応してもらえることで入会時やその他不明点が出てきた場合にも困ることなく問題を解決しやすくなります。
- 手続きが簡単
手続きが複雑だと、よく保険の内容を理解しないまま契約してしまうことになり、あとでトラブルに発展してしまうおそれがあります。そこで、わかりやすく簡単な手続きを採っている団体であるほうがよいでしょう。
上記の3つのポイントをカバーしているのが、一人親方団体労災センターです。一人親方の労災保険加入をサポートすべく、全国に支部を設けて対応しています。安心して申し込むことができるでしょう。
まとめ
一人親方とは、従業員を雇用せずに特定の業務に就く個人事業主のことを指します。特に多いのは、建築業界で働く一人親方です。
記事内で紹介したように、一人親方は会社員よりも多くの収入を得られる可能性を持ちます。ただし、安定して高収入を得るには、資格の取得や人脈形成なども大切です。
また、体制の整った団体を通じて一人親方労災保険を加入することで、ケガを負ったときなどでも補償を受けられ、事業を継続しやすくなります。
一人親方になることを検討している方は、是非この機会に労災保険についてもご確認くださいませ。