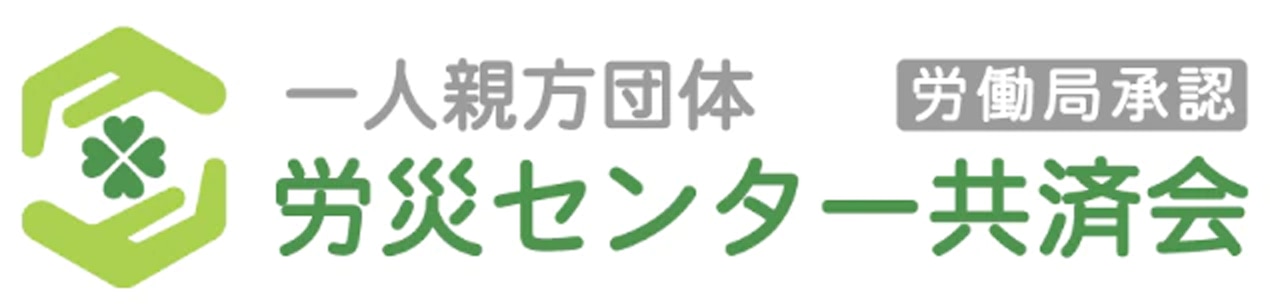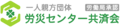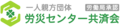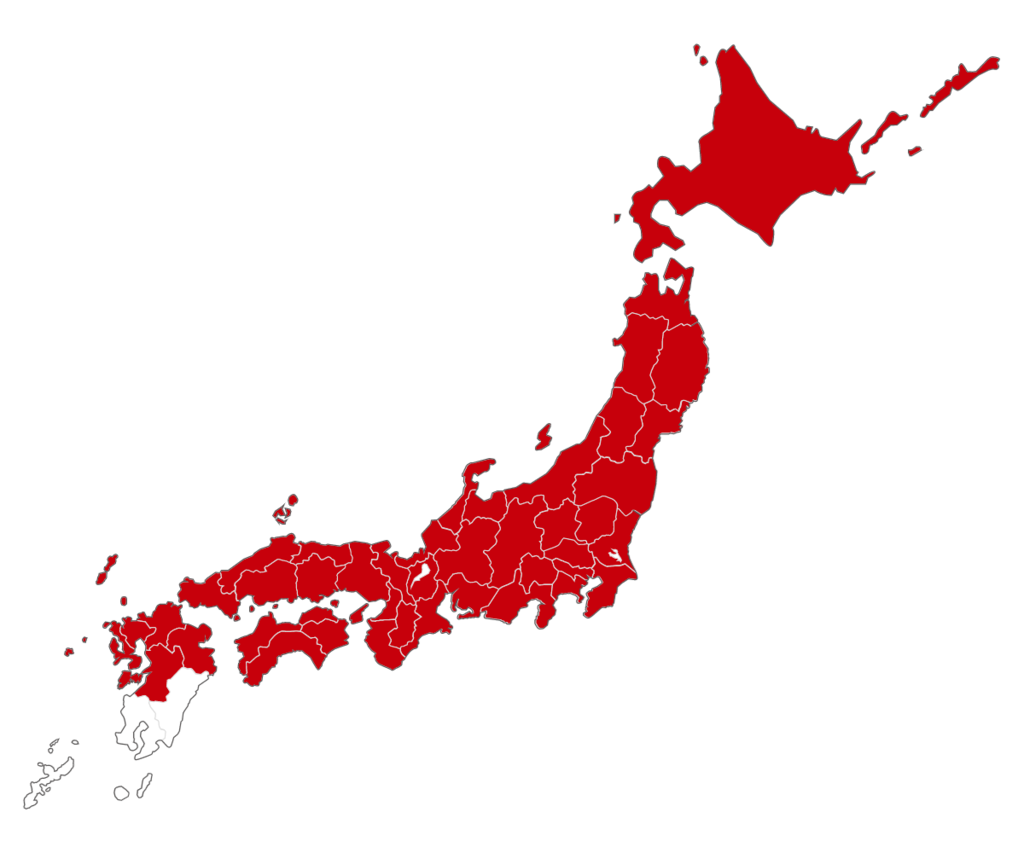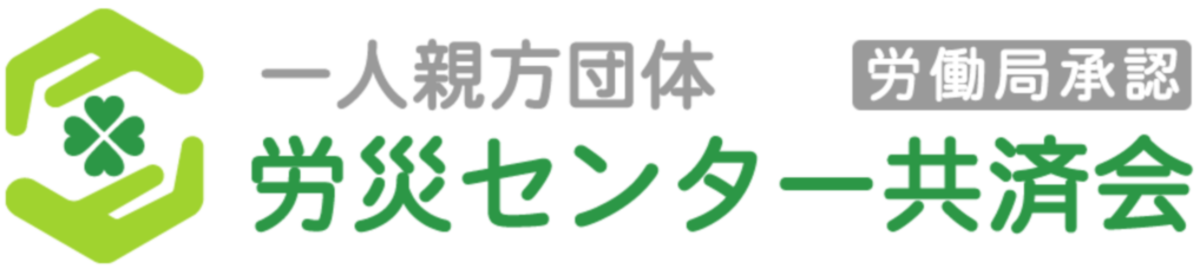
一人親方における労災保険の特別加入とは?仕組みやメリットを解説

一人親方は、本来なら労災保険に加入できませんが、業務の実態や労災事故の発生状況などを考慮し、任意で特別加入が認められています。特別加入すると労災事故について補償を受けられるため、自分や家族の負担を軽減できるほか、元請からの発注を受けやすくなります。
日本では、労働者が業務上または通勤途上で災害に遭い、ケガまたは病気になった場合、労働者本人またはその遺族に給付金を支払う「労働者災害補償保険(労災保険)」の制度が導入されています。
ただ、労災保険はあくまで適用事業者に使用されて賃金を支払われている労働者を対象としたものなので、自営業者や事業主、家族労働者は労災保険の補償を受けることができません。
特定の会社に属さない一人親方も、本来なら労災保険の適用対象外になりますが、特別加入制度を利用すれば、任意で労災保険に加入することが可能です。
今回は、一人親方労災保険の特別加入に関する基礎知識や、加入対象者、加入のメリットなどについて解説します。
目次[非表示]
そもそも労災保険とはどういう保険か?
労災保険は労働者の仕事中又は通勤途上での万が一の災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して補償するためのものです。労働基準法には療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等労災保険法と同じような補償の規定があります。事業主によっては補償能力が低いなど十分な補償が確保できなかったり、補償期間が長期化するなどしたりした場合、被災した労働者が不利益を被る可能性があります。労災事故が発生した場合、事業主によって補償に差が生じては労働者保護に欠けてしまいます。
そこで労働基準法の災害補償の規定を事業主から保険料を徴収して国が代行して行う制度として労災保険法が成立しました。つまり、労災保険法とは労働基準法の労働者保護をより実効性のあるものにするために国が主体となった保険形式の制度と言えます。
一人親方における労災保険の特別加入とは
一人親方とは本来自らの責任と能力で請け負ったお仕事を完成させます。そのため、他人に雇用されることを前提とした労災保険は一人親方に適用させる余地は全くないと言えます。しかし、一人親方として働く方は通勤や業務など外形的には一般労働者と変わりがない場合もあります。そこで、任意の組合を組織し一人親方をその組合員とした場合、組合を使用者、組合員である一人親方を労働者とみなして労災保険に加入させる道を拓きました。これが労災保険の特別加入制度です。
他の業種に比べて労災事故の発生件数が多い建設業界などで働く一人親方も、特別加入制度の対象者に含まれており、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体にて所定の手続きを行えば、労災保険に加入することが可能となります。
特別加入団体は全国各地に複数存在しているため、特別加入の申請を行う場合は、厚生労働省のHPに掲載されている「特別加入団体一覧表」を参考にするか、あるいは都道府県労働局または労働基準監督署へ問い合わせて、最寄りの特別加入団体を調べる必要があります。
労災保険の特別加入対象者と条件
一人親方労災保険への特別加入は、以下7つのうち、いずれかの事業を常態的に行う人を対象としています。
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送などを行う事業(個人タクシー、個人貨物運送業者など)
- 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊、解体またはその準備を行う事業(大工や左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕を行う事業
- 林業を行う事業
- 医薬品の配置販売を行う事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などを行う事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
なお、一人親方労災保険への特別加入にあたり、個人・法人は問いません。個人事業主または法人代表者として登録を行っている場合でも、一人で事業に従事している人は「一人親方」とみなされ、特別加入の対象となります。
労働者を使用する場合でも、使用日数が年間延べ100日未満の場合は、一人親方として労災保険に特別加入することが可能です。
特別加入のメリット

一人親方労災保険への特別加入は任意ですが、加入すると以下のようなメリットがあります。
業務上・通勤途上で発生した災害に対して給付金を受給できる
一人親方労災保険に特別加入していると、仕事中や通勤途上で発生した災害によってケガ・病気になった際、給付基礎日額に応じた額の補償を受けられます。
治療費に関しては、治療が終わるまで原則として全額支給されるほか、労災によって休業を余儀なくされた場合は、休業した日の4日目から、1日単位で給付基礎日額の8割の補償を受けられます。
労災によって障害が残り、介護を受けなければならなくなった場合は、月単位で介護補償を受けることが可能です。万が一、労災によって被保険者が死亡した場合は、遺族の生活補償として年金や一時金などが支給されます。
さらに被保険者の死亡により葬儀などを執り行った場合、埋葬料の給付を受けることができます。埋葬料は葬儀を執り行った本人が給付対象となるため、家族以外の人が葬儀を行った場合でも給付を受けることが可能です。
いずれのケースも労働者と変わらない補償を受けられるため、一人親方本人はもちろん、家族の負担も軽減できるところが大きな利点です。
仕事を受注しやすくなる
建設現場などでは、元請業者が現場単位で労災保険をかけるため、労働者は下請けも含めて労災保険の補償対象となります。
しかし、労働者とみなされない一人親方は労災保険の対象にならないため、現場で災害が発生し、負傷または病気にかかってしまったとしても、補償を受けることはできません。
特に建設業界は他の業種に比べて労働災害の発生率が高く、2019年には全体の3割強にあたる269人が死亡災害に遭い、15,000人以上が休業4日以上の死傷災害に見舞われています。[注1]
そのため、元請業者は万一のことを考慮し、仕事を発注するにあたって労災保険に特別加入しているかどうかを重要視します。労災保険に加入していれば、元請業者も安心して仕事を発注できるため、受注件数の増加にもつながるでしょう。
[注1]厚生労働省:平成31年/令和元年 労働災害発生状況
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/b19-16.pdf
労災保険の特別加入に必要な健康診断
一人親方労災保険に特別加入するにあたり、特定業務に一定年数以上従事した経験のある人は、加入時健康診断を受ける必要があります。
以下では、加入時健康診断が必要な業務と健康診断の種類を一覧にまとめました。[注2]
業務の種類 |
必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務3年以上従事した者 |
じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務に1年以上従事した者 |
振動障害健康診断 |
鉛業務に6ヶ月以上従事した者 |
鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務に6ヶ月以上従事した者 |
鉛中毒健康診断 |
上記の要件に該当する人は、特別加入団体宛に「特別加入時健康診断申出書」を提出します。
申出書の業務歴から加入時健康診断が必要と判断された場合、「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断実施依頼書」が交付されますので、指示書に記載された期間内に指定の健康診断を受けにいきます。
健康診断は労働局長が委託している診断実施機関でしか受診できませんので、最寄りの機関を事前に調べておきましょう。
なお、加入時健康診断の費用は国が負担してくれるので、自分で費用を用意する必要はありません。
ただし、実施機関までの交通費は自己負担となりますので要注意です。
[注2]厚生労働省:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
労災保険の特別加入に制限はある?
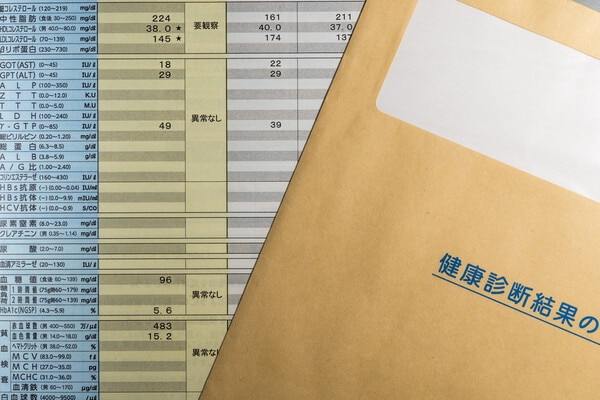
一人親方労災保険には年齢制限はありませんが、前節で紹介した加入時健康診断を受けた結果、以下のいずれかに該当する場合は加入を制限されます。[注2]
すでに疾病にかかっていて、その症状または障害によって一般的に就業することが困難であり、療養に専念しなければならない場合
- すでに疾病にかかっていて、その症状または障害によって当該業務からの転換が必要と認められる場合
1の場合は、従事する内容にかかわらず、一人親方労災保険への特別加入は認められません。
一方、2の場合は、加入時健康診断が必要な業種以外の業務についてのみ、特別加入が認められます。
労災保険の特別加入者の数と今後の課題
一人親方の従事者としては建設業が断然多く、およそ50万人から60万人の一人親方が労災保険に特別加入をしているとされています。次に多いのが自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業となります。個人タクシーや赤帽など街中でも見掛けることが多々あります。また、平成25年の労働基準局長の「自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の取扱いについて」の通達により、原動機付自転車も労災保険の特別加入の範囲に含まれることになり、今後ますます増加することが見込まれます。
数年前になりますが、ウーバーイーツの配達員が労働組合を結成したというニュースがありました。配達員とウーバーイーツとは雇用契約ではなく業務委託契約とのことで、仕事中に怪我をした場合ウーバーイーツからは治療費を上限25万円まで支払うとのことですが、やはり労災保険が適用されないのは厳しいです。なお、配達員は自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業と考えられ労災保険の特別加入に該当すると思われますが、配達員には自転車の方も多いと聞きます。自転車の場合は当然ながら労災保険の特別加入には該当しません。多様な働き方が拡大するにつれ、今後は労災保険の特別加入制度も同様に多様化する必要が出てくる思われます。
労災保険の特別加入に該当する職種が増えてくれば当然特別加入者の数も増加します。そしてそれに伴い偽装請負・偽装委託という問題も増えてきます。一人親方を使用する会社側に一層のモラルが求められることになるでしょう。
まとめ
一人親方は労災保険法における「労働者」には該当しませんが、特別加入制度の利用対象者に含まれているため、任意で労災保険に加入することが可能です。
労災保険に加入していないと、業務上または通勤途上で発生した災害によるケガや疾病に対する補償を受けられず、本人やその家族に大きな負担がかかってしまいます。
また、元請業者は労災保険に加入しているか否かを非常に重視しており、非加入者への発注は控える傾向にあります。
自分や家族の生活補償はもちろん、今後一人親方として事業を継続させていく意思があるのなら、特別加入制度を利用して労災保険に加入することをおすすめします。
一人親方が労災保険に特別加入するにあたって下記の点特に注意しましょう。
- 一人親方には給料というものがありません。そのため、あらかじめ定められた給付基礎日額というものを届け出る必要があります。
- 従業員を雇用した場合、一人親方の労災保険の加入を継続できなくなります。ただし、年間100日未満の雇用なら問題ありません。
- 粉塵を伴う作業、振動工具や鉛や有機溶剤を使用する業務に過去就いていた経験があってその年数が一定の年数を超える場合は健康診断の受診義務があります。
- 通常の労災保険の給付にはボーナスを基礎とする特別支給金がありますが、特別加入に限ってはボーナスというものがないので、ボーナスを基礎とする特別支給金はありません。
- 通常の労災保険は無記名の保険です。そのため、1日1時間でも働いた場合は働いた時間に対して労災保険料を支払います。しかし、特別加入の場合は特別加入者の名前、生年月日、従事する仕事の内容、給付基礎日額というのをあらかじめ任意の組合(一人親方団体)を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。