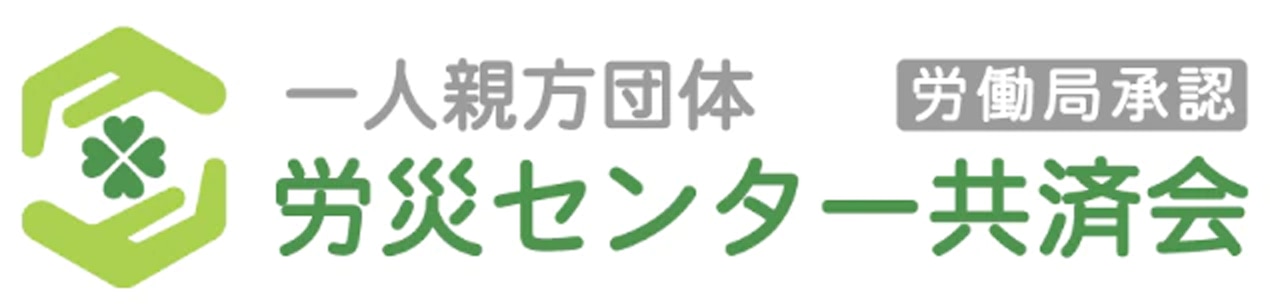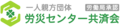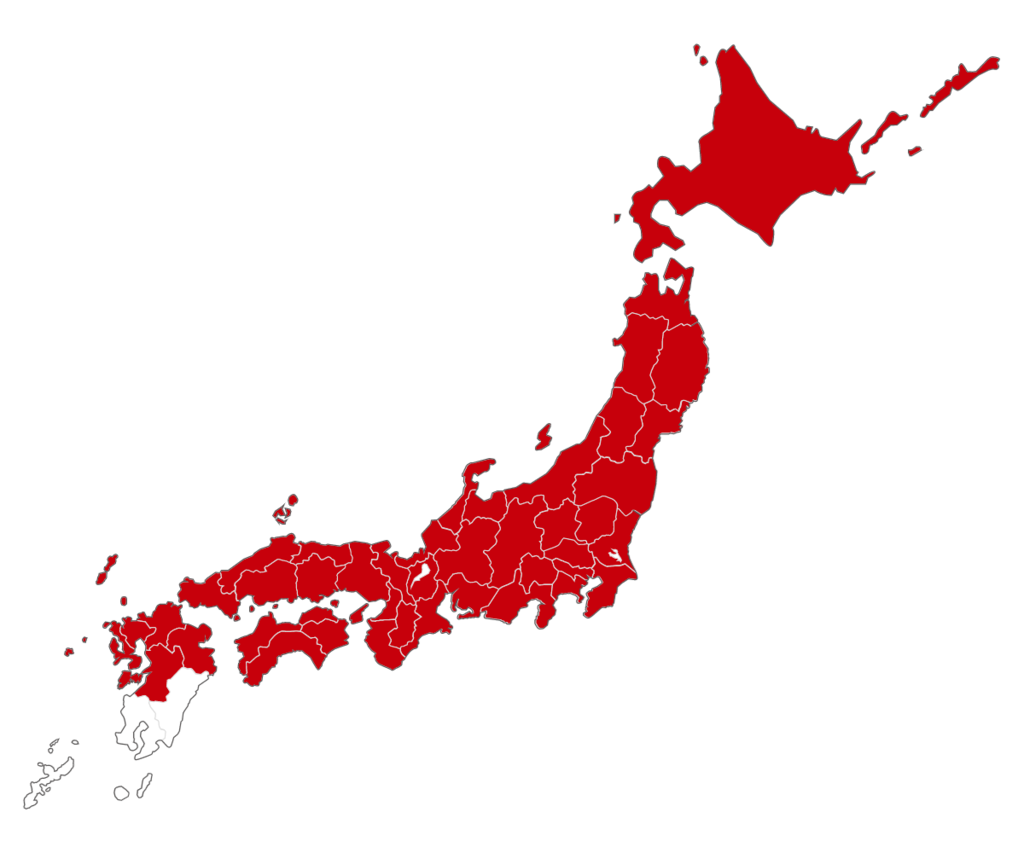労災保険の休業補償と、傷病手当金の違いを解説!給付金額はいくら?
「労災保険の休業補償と、健康保険の傷病手当金の違いは何?」
「両方同時に併給されることはある?」
この記事では、労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金に、どのような違いがあるのか解説しています。さらに、給付金額がいくらもらえるのか計算する方法や、両方を併給できるのかもまとめています。
最後までお読みいただければ、労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金の違いを、正しく理解できるでしょう。また記事の後半では、病気やケガなどの際に受け取れる、その他の給付制度についても解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.労災保険の休業補償と、健康保険の傷病手当金の違い
- 2.労災保険の休業補償と傷病手当金の併給はない|どっちの補償を受けられる?
- 3.補償金額はいくらもらえる?支給期間は?
- 3.1.労災保険の休業補償の場合
- 3.1.1.給付基礎日額とは
- 3.1.2.業務災害の場合、休業3日目までは会社から補償を受けられる
- 3.2.健康保険の傷病手当金の場合
- 3.2.1.傷病手当金がもらえるのは通算1年6ヶ月まで
- 4.健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」の違い
- 5.休職時の補償以外で覚えておきたい給付制度
- 5.1.傷病(補償)等年金|労災保険
- 5.2.介護(補償)等給付|労災保険
- 5.3.障害(補償)等給付|労災保険
- 5.4.遺族(補償)等給付|労災保険
- 5.5.障害年金|厚生年金・国民年金
- 5.6.遺族年金|厚生年金・国民年金
- 6.まとめ
労災保険の休業補償と、健康保険の傷病手当金の違い
まず大前提として整理しておきたいのは、「傷病手当金」は労災保険の制度ではなく、健康保険からの給付金である点です。労災と傷病手当金は別の制度であることを踏まえて、それぞれの概要を見てみましょう。
労災保険とは、業務上の病気やケガに備える保険
労災保険とは、労働者が業務上の病気やケガを被った場合に、補償を受けられる保険です。勤務時間中の事故はもちろん、過労による病気や通勤途中の事故なども、補償の対象となっています。
労災保険を管掌しているのは厚生労働省であり、正社員や契約社員はもちろん、派遣社員やパート、アルバイトなど全ての労働者が適用対象となります。ただし、社長や役員、個人事業主など労働者でない人は、「特別加入」という例外を除き、原則として労災保険の対象にはなりません。
傷病手当金とは、プライベートの病気やケガで会社を休む時にもらえる給付金
傷病手当金は、プライベート(業務に起因しない)の病気やケガで休職を余儀なくされた時にもらえる給付金です。傷病手当金を受け取れるのは、3日間の待機期間を経て休業4日目からであり、健康保険から支給されます。ただし、任意継続被保険者の方は傷病手当金の支給対象外です。
傷病手当金の受け取りには要件があり、自己判断で会社を休む場合には支給されません。医師の指示による休業が条件であり、傷病手当金の手続きには医師の証明が必要です。
業務上の病気やケガとは|通勤中の事故も労災保険の対象
業務上の病気やケガは、専門的には「労働災害」と呼ばれます。労働災害には業務災害と通勤災害の2種類があり、業務に起因する病気やケガは業務災害、出勤や帰宅途中の事故などは通勤災害に分類されます。
病気やケガが業務上のものであるかは、仕事と病気・ケガに因果関係があるかどうかで判断されます。勤務時間中のケガなどはわかりやすい例ですが、仕事が原因でうつ病を発症した場合などは、労災認定されれば労災保険から補償が受けられます。
労災保険の休業補償と傷病手当金の併給はない|どっちの補償を受けられる?

労災保険には、業務上の病気やケガで会社を休んだ時に受け取れる、休業補償給付と呼ばれる補償があります。医師の指示で会社を休んだ時に受け取れる点は、健康保険の傷病手当金と共通していますが、残念ながら両方同時に併給されることはありません。
なぜなら、労災保険の休業補償は業務上の病気やケガが対象である一方、健康保険の傷病手当金は業務上のものを除いた病気やケガが対象であり、補償対象が異なるためです。このことは、傷病手当金の礎となる健康保険法の第1条に明記されています。
【引用部分】
第一条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
引用:健康保険法/e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070
労災保険の休業補償を受給中の人は傷病手当金を受け取れない
仕事ではない原因で病気やケガを被った際、すでに別の原因で労災保険の休業補償を受け取っている場合、傷病手当金が併給されることはありません。
ただしその場合、労災保険の休業補償で受け取っている金額が、傷病手当金の給付額よりも少ない時には、差額分の支給を受けられます。
補償金額はいくらもらえる?支給期間は?
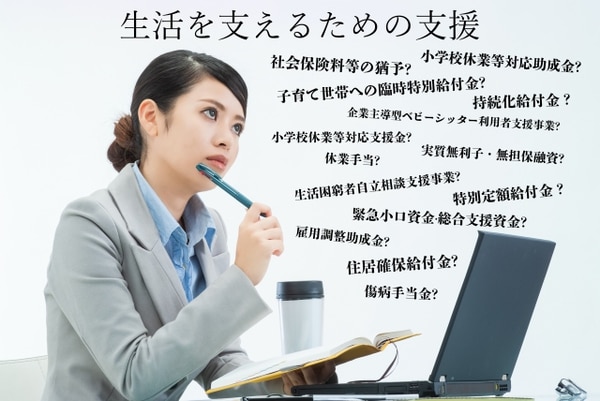
労災保険の休業補償と、健康保険の傷病手当金には、いくらの補償金額が用意されているのでしょうか。労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金、それぞれの補償金額について、詳しく解説します。
労災保険の休業補償の場合
労災保険の休業補償では、医師の指示で会社を休んだ4日目から、1日につき給付基礎日額の60%が支払われます。さらに、「休業特別支給金」と呼ばれる制度により、1日につき給付基礎日額の20%が上乗せされます。
つまり労災保険の休業補償では、1日につき給付基礎日額の80%の給付がもらえます。
給付基礎日額とは
労災保険の休業補償の算出に用いられる給付基礎日額とは、労働基準法における平均賃金を指します。労働災害が発生した日の直前3ヶ月間に受け取った賃金の総額を、期間中の暦日数で割った金額が、給付基礎日額です。
例えば、月給30万円の人が6月に業務上の理由でケガをしたと仮定すると、平均賃金(給付基礎日額)は3月〜5月の給料から計算します。
30万円×3ヶ月÷(3月:31日+4月:30日+5月:31日)=9,783円(平均賃金) ※端数切り上げ
平均賃金(給付基礎日額)が9,783円と求められたので、労災保険の休業補償で受け取れる金額を計算してみましょう。
- 休業補償:9,783円×60%=5,869円 ※端数切り捨て
- 特別支給金:9,783円×20%=1,956円 ※端数切り捨て
上記2種類を合計すると、労災保険の休業補償でもらえる金額は、1日あたり7,825円となります。
業務災害の場合、休業3日目までは会社から補償を受けられる
労災保険に認定された理由が業務災害の場合、休業3日目までは会社から補償金を受け取れます。受け取れる金額は平均賃金の60%であり、労災保険からではなく、会社から支払われる補償金です。
休業3日目までは会社から補償金を受け取れる理由は、労働基準法の第76条で、業務災害による休業時は会社負担で補償をするよう義務付けられているためです。
【引用部分】
労働基準法 第76条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
引用:労働基準法(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
休業4日目からは労災保険による補償が受けられるため、会社負担の補償は原則としてなくなります。なお通勤中の事故でケガをした場合は、会社が休業補償を負担する義務がないため、補償金はもらえません。
健康保険の傷病手当金の場合
健康保険の傷病手当金は、医師の指示で会社を休んだ4日目から、1日あたり下記の計算式で算出される金額を受け取れます。
【引用部分】
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
引用:傷病手当金/全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/
- なお傷病手当金の計算に用いる「標準報酬月額」とは、社会保険料などの計算をしやすくするために、報酬月額をきりのいい幅で区分した金額です。月給とは若干の差が生まれますが、おおよそ自分の月給程度の金額と考えればよいでしょう。
つまり健康保険の傷病手当金は1日あたり、月給を30日で割った金額の3分の2程度と計算できます。仮に月給が30万円の人であれば、30万円÷30日×3分の2=約6,666円/日の傷病手当金がもらえます。
これまでの試算でわかるように、労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金では、労災保険の休業補償の方が受け取れる金額は多くなっています。
傷病手当金がもらえるのは通算1年6ヶ月まで
健康保険の傷病手当金がもらえるのは、支給開始日から通算して1年6ヶ月までとなります。受給期間中に仕事に復帰して、再び同じ病気・ケガで休職する場合は、復帰前の期間と合計して1年6ヶ月までが支給期間となります。支給期間を過ぎると傷病手当金は打ち切り(終了)となり、以降の支給はありません。
健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」の違い
健康保険の傷病手当金に似たものに、雇用保険の「傷病手当」があります。健康保険と雇用保険は別の保険であり、両者は補償内容や条件の異なる別の制度です。
雇用保険の傷病手当とは、ハローワーク(公共職業安定所)へ求職の申し込みをした後に、病気やケガが原因で15日以上にわたり仕事ができない場合にもらえる給付金です。
なお雇用保険の傷病手当は、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業給付を受け取っている場合に、併給されることはありません。
休職時の補償以外で覚えておきたい給付制度
病気やケガを被った時には、労災保険の休業補償や健康保険の傷病手当金の他に、覚えておきたい給付制度がいくつもあります。それぞれの給付制度ごとに受け取れる条件は違いますが、知らないと損をする可能性もあるので、ぜひチェックしてみてください。
傷病(補償)等年金|労災保険
労災保険の傷病(補償)等年金は、労働災害に起因する病気やケガが1年6ヶ月を経過しても治癒しておらず、かつ傷病等級に該当する場合に受け取れる年金です。傷病等級に応じて給付基礎日額の245〜313日分の年金を受け取れ、さらに傷病特別支給金や傷病特別年金の支給があります。
なお傷病(補償)等年金の給付が決定した場合は、労災保険の休業補償から切り替えられる形となり、併給はありません。また業務上の災害に起因する補償のため、傷病手当金との併給もありません。
介護(補償)等給付|労災保険
労災保険の介護(補償)等給付は、労働災害が原因で一定の条件を満たした場合、介護費用を保証してもらえる制度です。支払った介護費用が全額補償され(上限あり)、常時介護と随時介護、また親族による介護などの状況によって金額が変わります。
こちらも労災保険の制度なので、傷病手当金との併給はないです。
障害(補償)等給付|労災保険
労災保険の障害(補償)等給付は、労働災害により被った病気やケガが症状固定した後に、障害等級に該当する後遺障害が残った場合に受け取れる補償です。
「障害(補償)等年金」と「障害(補償)等一時金」の2種類があり、後遺障害の程度によって受け取れる給付とその金額が変わります。
労災保険の制度であるため、健康保険の傷病手当金との併給はありません。
遺族(補償)等給付|労災保険
労災保険の遺族(補償)等給付は、労働災害に起因する病気やケガで労働者が死亡した場合に、遺族が受け取れる給付です。「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」があり、基本的には遺族(補償)等年金の方を受け取る形となります。
障害年金|厚生年金・国民年金
障害年金は、厚生年金または国民年金に加入していた人が受け取れる年金制度です。病気やケガで規定の後遺障害が残った場合、現役世代であっても年金を受け取れます。
なお厚生年金・国民年金の障害年金と、労災保険の障害(補償)等年金の両方に認定された場合は、労災給付の方を調整した上で併給される仕組みです。また、健康保険の傷病手当金を受け取っている場合も、調整の上で併給されます。
遺族年金|厚生年金・国民年金
遺族年金は、厚生年金または国民年金に加入している(加入していた)人が死亡した場合に、遺族が受け取れる年金制度です。亡くなった方の納付状況などに応じて、その人により生計が維持されていた遺族が年金を受け取れます。
なお労災保険の遺族(補償)等給付の条件も満たしている場合は、労災側の支給額が調整された上での併給が可能です。
まとめ
病気やケガで受け取れる給付制度を正しく理解しよう
この記事では、労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金の違いや、併給可能かどうかなどを解説しました。記事の要点をごく簡単にまとめると、次のとおりです。
- 労災保険の休業補償は、業務に起因する病気やケガで休職する際に受け取れる
- 健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで休職する際に受け取れる
- 労災保険の休業補償と健康保険の傷病手当金は、併給されることはない
- 計算方法は異なり、健康保険の傷病手当金より労災保険の休業補償の方が多くもらえる
- 雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の傷病手当金とは別の制度
記事内でも紹介したように、労災保険や傷病手当金以外に、病気やケガを被った際に受け取れる給付制度はたくさんあります。労災や傷病手当金以外の制度についても正しく理解し、もらえる給付は全て漏れなく受け取るようにしましょう。
- 一人親方には、万が一に備えて労災保険への特別加入がおすすめ
労災保険に入っていると、万が一の際にも安心
- 一人親方団体労災センター共済会は、費用を抑えて迅速に加入できるのでおすすめ
一人親方労災保険の特別加入の手続き方法詳細はこちらから