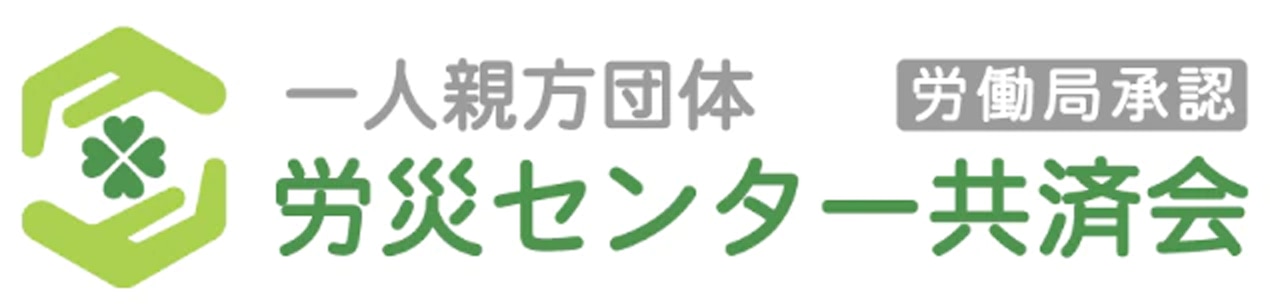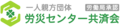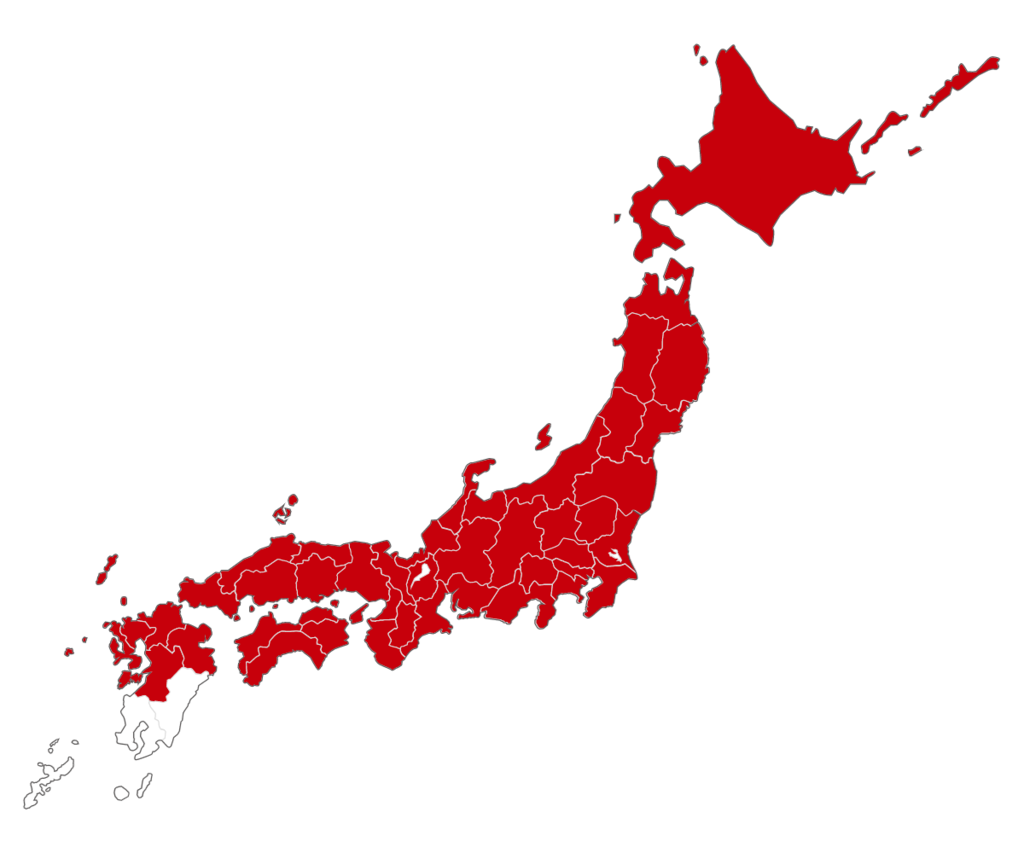労災保険法とは?法律の要点や改正、特別加入制度などをわかりやすく解説
この記事では、労災保険法の概要を短時間で確認できるよう、法律の要点をわかりやすく簡単に解説しています。労災保険法の概要や対象者、補償・保険給付の種類などを総合的に確認可能です。
さらに、最近の労災保険法の改正のポイントや、特別加入制度の概要、労働基準法との関係や違いも解説しています。最後までお読みいただければ、きっと労災保険法に関する疑問を解消できるでしょう。
目次[非表示]
労災保険法(労働者災害補償保険法)とは

労災保険法とは、正式名称を「労働者災害補償保険法」と呼び、労災保険の制度について定めた法律です。仕事に起因する病気やケガを被った労働者の社会復帰や、その遺族を支援すること、さらに安全な労働環境を作ることなどが、法律の目的とされています。
労災保険法を管掌しているのは、厚生労働省すなわち政府です。各種手続きや保険料の納付などは、全国の労働基準監督署や労働局などでおこないます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律について
労災保険法に関連する法律に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(以下、徴収法)があります。徴収法は、労働保険を効率よく運営するために定められた法律です。法律の中身は、労働保険の成立手続きや保険料の納付などに関する内容となっています。
なお労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」という2つの保険制度の総称です。つまり労働保険の保険料の徴収等に関する法律には、労災保険だけでなく雇用保険に関する取り決めも記載されています。
法律の要点は?労災保険の制度概要を解説
労災保険法は、全ての労働者が安心して働けるように用意されている、労災保険の制度について定めた法律です。こちらでは労災保険法の要点を把握できるように、労災保険の制度概要を解説していきます。
労災保険法に定められる「労災保険」とは
労災保険は、労働者や遺族を労働災害から守るための保険です。もし労働者が仕事に起因する病気やケガを被った時は、自己負担なしで必要な治療を受けられ、やむを得ず休職する場合は休業補償金が給付されます。
その他にも多彩な補償や給付が用意されていて、労働者はもし労働災害の被害を受けても、手厚い支援を受けられます。
労働災害とは|業務災害と通勤災害の違い
労災保険法を理解するためには、「労働災害」の意味を知っておく必要があります。労働災害とは、業務災害と通勤災害の総称です。
業務災害とは、業務上の理由で生じた病気やケガ、死亡などの災害です。勤務中に負傷した場合や、過労が原因で精神疾患を発症した場合などが、業務災害に該当します。
通勤災害とは、労働者の通勤により生じた病気やケガ、死亡などの災害です。通勤中に転んでケガをした場合や、交通事故の被害を受けた場合などが、通勤災害に該当します。ただし通勤災害が認定されるためには、通勤ルートを逸脱していないなどの条件があります。
労災保険の補償内容と、受けられる給付の種類
労災保険法で定められている労働者に対する補償は非常に手厚く、用意されている給付の種類は多岐にわたります。労災保険法で定められた給付一覧は、次のとおりです。
- 療養(補償)等給付
- 休業(補償)等給付
- 障害(補償)等年金
- 障害(補償)等一時金
- 遺族(補償)等年金
- 遺族(補償)等一時金
- 葬祭料等(葬祭給付)
- 傷病(補償)等年金
- 介護(補償)等給付
- 二次健康診断等給付
労災保険法に定められた、それぞれの補償や給付の概要は、次のとおりです。
給付の種類 |
概要 |
給付金額 |
特別支給金 |
|---|---|---|---|
療養(補償)等給付 |
病気やケガを被った時に、必要な治療を受けられる補償 |
必要な療養、または必要な療養費用 |
|
休業(補償)等給付 |
医師の指示で休職する場合に受けられる補償 |
休業1日につき、給付基礎日額の60% |
「休業特別支給金」 休業4日目以降、休業1日につき、給付基礎日額の20% |
障害(補償)等年金 |
病気やケガが治癒し、障害等級の第1級~第7級の後遺障害が残った時に受け取れる年金 |
障害等級に応じ、給付基礎日額の131~313日分の年金 |
「障害特別支給金」 障害等級に応じ、159~342万円の一時金 「障害特別年金」 障害等級に応じ、算定基礎日額の131~313日分の年金 |
障害(補償)等一時金 |
病気やケガが治癒し、障害等級の第8級~第14級の後遺障害が残った時に受け取れる一時金 |
障害等級に応じ、給付基礎日額の56~503日分の一時金 |
「障害特別支給金」 障害等級に応じ、8~65万円の一時金 「障害特別一時金」 障害等級に応じ、算定基礎日額の56~503日分の一時金 |
遺族(補償)等年金 |
労働者が死亡した時、遺族が受け取れる年金 |
遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153~245日分の年金 |
「遺族特別支給金」 遺族の人数によらず、一律300万円 「遺族特別年金」 遺族の人数に応じて、算定基礎日額の153~245日分の年金 |
遺族(補償)等一時金 |
遺族(補償)等年金の受給資格がある遺族がいない時に、遺族が受け取れる一時金 |
給付基礎日額の1,000日分の一時金 または1,000日分の一時金から支給済み年金合計額を控除した額 |
「遺族特別支給金」 遺族の人数によらず、一律300万円 「遺族特別年金」 算定基礎日額の1,000日分の一時金 または1,000日分の一時金から支給済み特別年金合計額を控除した額 |
葬祭料等(葬祭給付) |
死亡した労働者の葬祭をおこなう時に受け取れる給付 |
315,000円+給付基礎日額の30日分 ただし、上記合計が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分 |
|
傷病(補償)等年金 |
病気やケガの療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合に受け取れる年金 |
傷病等級に応じ、給付基礎日額の245~313日分の年金 |
「傷病特別支給金」 傷病等級に応じ、100~114万円の一時金 「傷病特別年金」 傷病等級に応じ、算定基礎日額の245~313日分 |
介護(補償)等給付 |
障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、条件を満たすと受けられる介護費用の補償 |
常時介護の場合、月あたり73,090円~171,650円 随時介護の場合、月あたり36,500円~85,780円 |
|
二次健康診断等給付 |
会社の健康診断で特定の異常が認められた時に、二次健康診断を受けられる補償 |
二次健康診断および特定保健指導の給付 |
労働者を雇う事業主は加入義務があり、保険料は全額会社負担
労災保険に加入するのは、労働者個人ではなく事業主です。労働者を1人でも1日でも雇用する事業主は、全て労災保険への加入義務があります。
【引用部分】
第三条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
引用:労働者災害補償保険法/e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050_20200901_502AC0000000014
また労災保険法および徴収法により、保険に加入することで生じる保険料は、全額が事業主負担となります。労働者が労災保険料を負担することはなく、保険料は全て事業主が支払います。
労災保険の対象となる人
労災保険法では、「労働者」が補償の対象となると定められています。労災保険法における労働者とは、事業主と雇用関係にある人です。労災保険の対象となる人の例と、ならない人の例を紹介すると、次のとおりです。
対象となる人の例 |
対象とならない人の例(例外あり) |
|
|
このように労災保険法の労働者には、正社員だけでなくパートやアルバイトなども含まれます。勤務日数や勤務時間によらず、雇用関係が成立する労働者は全員が労災保険法で保護される仕組みです。
一方、法人経営者や会社役員、個人事業主などは、事業主に雇用されているわけではないため、原則として労災保険の対象外となります。しかし労災保険法には「特別加入」と呼ばれる制度があり、一部の人については特別加入制度を利用することで、労働者と同様の補償を受けられます。
令和2年9月1日に労災保険法が改正!副業者や兼業者の補償が手厚くなった
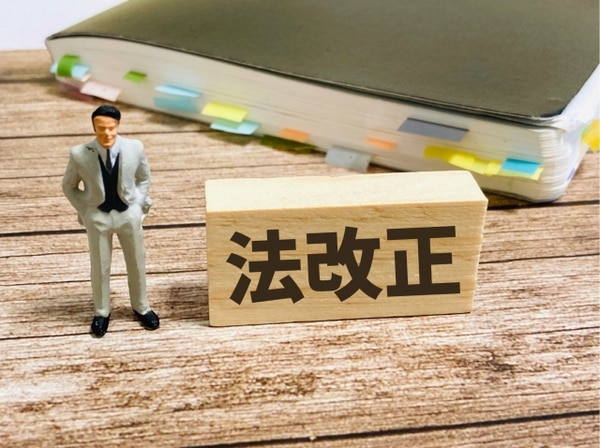
労災保険法は令和2年9月1日に改正され、副業や兼業をしている人に対する補償が、より手厚くなりました。令和2年9月1日の労災保険法の改正のポイントを解説します。
改正の対象となる人
令和2年9月1日の労災保険法改正の対象となる人は、複数の会社で雇用され、仕事をしている人です。個人事業主として副業をしている人は、原則として対象外ですが、労災保険に特別加入している人は対象となります。
全勤務先の賃金の合計金額をもとに給付額が算定される
令和2年9月1日の労災保険法の改正後には、複数の会社で働いている人に対する給付額が、全ての会社の賃金の合計金額をもとに算定されるようになりました。改正前には、労働災害が発生した会社の賃金額のみをもとに計算されていたため、労働者はより多くの給付額を受け取れるようになります。
労災認定時は全勤務先の負荷が総合的に考慮される
令和2年9月1日の労災保険法の改正により、複数の会社で働いている人に対する、労災認定の基準も変化しました。改正前には個別の勤務先ごとの負荷をもとに、労災認定がおこなわれていました。しかし改正後には、全ての勤務先の負荷が総合的に考慮され、労災認定がなされるようになります。
経営者や役員、個人事業主が利用できる特別加入制度
労災保険法により保護されるのは、原則として事業主と雇用関係にある労働者に限られます。会社に雇用されるわけではない、経営者や役員、個人事業主などは、基本的には労災保険法の対象外です。
しかしそういった労災保険法の対象外となる人でも、「特別加入」と呼ばれる制度を利用すれば、例外的に労災保険に加入できるようになっています。特別加入制度は、労災保険法の第4章の2に定められています。
労災保険に特別加入するための条件
労災保険法の特別加入制度を利用できるのは、下記いずれかに当てはまる人です。
- 中小事業主等
- 一人親方等
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
一般的に、法人の経営者や役員は中小事業主等に該当し、個人事業主は一人親方等に該当します。ただし個別のケースにより当てはまる分類は異なるため、厚生労働省が公開している「特別加入制度のしおり」などで確認しましょう。
労災保険に特別加入できる条件は、上記のどの分類に該当するかで異なります。例えば中小事業主であれば常時雇用している労働者の人数や、労働保険事務組合への委託などが条件です。
一方の一人親方等の場合、おこなっている事業の種類により加入可否が変わります。また加入時は労働局長の認定を受けた団体を通して加入する必要があり、中小事業主とは条件が違うため注意が必要です。
令和3年4月1日の法改正で特別加入の対象者が拡大
令和3年4月1日に労災保険法の一部が改正され、特別加入の対象者が拡大しました。令和3年4月1日の労災保険法の改正により、新たに特別加入の対象となる人は、次のとおりです。
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づき事業を行う方
令和3年9月1日にはさらに対象者が拡大
労災保険法はさらに改正され、令和3年9月1日からはより多くの対象者が特別加入制度を利用できるようになりました。令和3年9月1日の労災保険法の改正により、新たに特別加入の対象となった人は、次のとおりです。
- 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
- ITフリーランス
労働基準法との関係や違いを簡単に解説
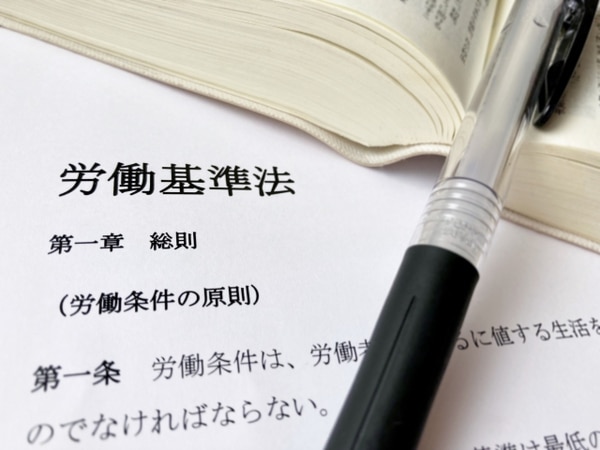
労災保険法について理解する際に、労働基準法との関係や違いを疑問に感じる人もいるでしょう。労働基準法とは、労働者が不当な労働を強制されないように、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。労働基準法が定められている目的は、全ての労働者を保護するためです。
労働基準法の第8章では、災害補償に関する事項が定められています。労働基準法によると、故意・過失に関わらず、労働者が業務上の病気やケガを被った場合、使用者には災害補償をおこなう義務があります。
労働基準法で定められた、使用者の災害補償義務が確実に履行されるように制定されたのが、労災保険法です。労働基準法の第84条には次のように記載されていて、労災保険法などにより労働者への災害補償が実施される場合、使用者の補償義務が免除される仕組みとなっています。
【引用部分】
第八十四条(他の法律との関係)
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
引用:労働基準法/e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
上記から労災保険法は、労働基準法で定められた災害補償の義務を代行しているものと解釈できます。
まとめ
労災保険法があるからこそ安心の労働環境が作られる
この記事では、労災保険法の概要や重要なポイントを、わかりやすく解説しました。記事の要点を簡単にまとめると、次のとおりです。
- 労災保険法とは、業務上の病気やケガを被った人や、その遺族に対する補償を定めた法律
- 人を雇用する事業主は労災保険への加入義務があり、保険料も全額負担する
- 労災保険法の対象となるのは、事業主と雇用関係にある労働者
- 経営者や役員、個人事業主は対象外であるものの、条件を満たせば特別加入できる
- 近年の法律改正により、兼業者への補償が手厚くなり、特別加入の範囲が拡大した
- 労災保険法は、労働基準法で定められた使用者の災害義務を代行する法律
労災保険法があるからこそ、労働者は安心して仕事をすることができ、事業主にとっても災害補償の負担を軽減できるメリットがあります。労災保険法は、労働者にとっても事業主にとっても、安心な労働環境づくりに貢献してくれる法律なのです。